「千利休」は豊臣政権におけるフィクサーだった!
- 2021/02/22

千利休(せんのりきゅう)と言えば、豊臣秀吉の茶頭にして天下一の茶人と評される人物である。その知名度は秀吉に匹敵するものであるにもかかわらず、その人物像は「芸術家肌の気難しい人」程度の認識しかされていないのが実状であろう。
しかし、実際の利休は孤高の人物ではなく、もっと人間臭い人物であったようだ。彼が何故非業の死を遂げることになったのかまで含めて、その人物像を史料から探ってみたい。
しかし、実際の利休は孤高の人物ではなく、もっと人間臭い人物であったようだ。彼が何故非業の死を遂げることになったのかまで含めて、その人物像を史料から探ってみたい。
貧しかった青年時代
千利休は大永2(1522)年、堺の商家に田中与兵衛の子として生を受けた。父与兵衛は魚屋(ととや)という屋号で商いを営んでいたという。魚屋は名前の通り、塩魚を扱っていたとも、魚を扱う商人に倉庫を貸す「問」を営んでいたとも言われる。そもそもは裕福だったと思われるが、当時は応仁の乱後の混乱がまだ続いており、座など、商人がかつて持っていた独占権が担保されず商いは年々厳しくなっていた。そんな中、利休は父と祖父を相次いで失うという不幸に見舞われる。このとき利休は19歳であったという。
その後、利休の生活は次第に困窮していったようだ。『緑苔墨跡』によると資金不足のため祖父の7回忌の法要が営めず、涙を流して墓掃除をしたとの記述がある。
茶の湯
茶の湯との出会いは17歳のときとされている。利休が茶の湯を習い始めたのは17歳の時と言われているが、『堺数寄者の物語』によれぱ、その最初の師は北向道陳であるという。 2番目の師については諸説ある。
『南方録』では、武野紹鴎(たけのじょうおう)に師事したとされているのであるが、この辺りの記述が『南方録』の元となった『堺鏡』には存在しない。 さらに『山上宗二記』の記述から判断すると2番目の師は紹鷗でなく、辻玄哉だった可能性があるという。
あわせて読みたい
茶の湯の修行は順調に進み、天文13(1544)年には松屋久政らを招いて茶会を開いたという記述が『松屋会記』にある。これが信頼できる史料の中では一番古い利休の茶会と言われる。
この時期、利休は珠光茶碗を好んで用いたようだ。というのも、『松屋会記』に記されている茶会の記録に珠光茶碗を用いたとあるからである。
珠光茶碗とは、「わび茶」の創始者と言われている珠光(じゅこう)伝来の茶碗で、そもそもは青磁を焼く工程において、酸化反応が強く出てしまったものである。珠光茶碗の写真を見ると、褪せた褐色が何とも言えない味わいを醸しだしていように思われるのだ。
利休の感性は早くから「わび茶」に反応していたようである。
三好氏の御用商人に
利休というと、世間とあまり関わりを持たない孤高の人物というイメージが、あまりに強いように思われる。ところが、史料の中の利休はどちらかというと社交的であり、ある意味野心家ですらある。当時、京で実権を握っていた三好長慶に近づき、その妹を妻に娶った。そのつてで三好家の御用商人となり、まずは、商売の道で成功を納めたといわれる。三好家と利休の関係は浅からぬものであったようだ。
利休の法名である宗易は大林宗套が名付けたと言われる。宗套は南宗寺を開いたことで知られるが、これを依頼したのが三好長慶だという。また、大徳寺聚光院は三好長慶を弔うため息子の義継が建立したものであるが、そこには千家の墓がある。
その一方で、松永久秀の茶会にも度々出席していたことも知られている。当時、堺で会合衆の1人となっていた利休は人脈作りに励んでいたものと思われる。
そんな中、利休はその運命を大きく変えることになる人物に出会う。
織田信長である。

信長の茶頭
信長は永禄11(1568)年、将軍足利義昭を奉じて上洛。その直後、今井宗久ら会衆に堺へ2万貫文の矢銭(軍資金)を要求したのである。宗久はこの件を了承し、以後信長に急接近する。利休は宗久らを介して信長と面会したと思われる。この頃は今井宗久と津田宗及が茶の湯の両巨頭であり、利休はまだ3番手に甘んじていたようだ。なにせ、両者とも所有する名物茶器の数や人脈などがずば抜けていたのだから当然であろう。
まずは津田宗及であるが、彼の父は茶の湯の達人・津田宗達である。血筋からしてサラブレッドの宗及は、その所有する名物茶道具が30種類を優に超え、信長も一目置く茶人であったという。
あわせて読みたい
因みに、利休は「なつめ」という茶器をしばしば用い、これを流行らせた人物として知られる。実は、この「なつめ」を利休に先んじて使用したのが宗及であった。
次に今井宗久であるが、彼は利休の茶の師匠とも言われる武野紹鴎の娘婿である。そのつてで武野家の茶道具を引き継いだようだ。
また、会合衆の中で先んじて信長との融和策を進めるなどの先見性にも長けていた。当時、堺随一の富豪であったという説すらある。
あわせて読みたい
一方、史料に見える利休所有の茶道具といえば、「善好香炉」、「珠光茶碗」、「圜悟墨跡」の掛け軸、「つるのはし」という古銅の花入、「手桶」の水指などが挙げられる。
2巨頭の所有する茶道具と比べると、かなり見劣りする感は否めない。利休が、これら2巨頭と互していくには人脈の開拓と圧倒的な創意工夫しかなかったのではないか。
例えば、利休は善好香炉を袋に入れて床の間に飾っておき、客人が入室してからそれを取り出して、目の前で香を炷くという作意を好んだという。これは当時、画期的な発想であったようだ。
そんな利休にとって、新しもの好きの信長はうってつけの人物であったろう。そう考えると、利休は三好長慶の死後は意図的に信長に近づいていったように思えてならない。
1570年代に入ると利休が信長の茶会に出席したとの記述が史料に現れ始める。
『今井宗久茶湯抜書』には、天正2(1574)年3月24日の茶会において、茶事の後、今井宗久・津田宗及・千易(利休)の3名が、書院にて千鳥の香炉を特別に拝見したとの記述が見られる。
この頃には既に信長の茶頭の1人として仕えていたものと思われる。同じ頃、利休は宗及とともに、かの「蘭奢待」を信長から下賜されていて、その厚遇ぶりが窺えよう。
利休は越前一向一揆の際には、信長に鉄砲の玉を1000ほど都合するなど、武器商人としても貢献している。
信長の利休に対する信頼度は日増しに大きくなっていったのではないか。そして、遂に利休の名が『信長公記』に登場するようになる。
『信長公記』によると、石山本願寺と和睦した1週間後の天正3(1575)年10月28日信長は妙覚寺において茶会を開いているが、その茶頭は利休であった。この茶会は京や堺の茶人17名が招かれた盛大なものであった。その席では、本願寺顕如が献上した「三日月」や「松島」などの茶壺、「九十九髪」の茶入れなどが披露されたという。
この、いわば戦勝祝賀セレモニー的な茶会において、利休が茶頭を務めたということは重要なターニングポイントだと思われる。信長の目には利休が茶頭筆頭と映っていたのではないか。
豊臣政権
天正10(1582)年6月2日本能寺の変が勃発し、信長は倒れる。その後、秀吉が中国大返しによって、尋常でないスピードで畿内に戻って山崎の戦いで明智光秀を破り、続いて翌年の賤ヶ岳の戦いを経て信長の後継者としての地位を確立していく。天正11(1583)年3月8日付の『末吉勘兵衛宛利休書状』によれば、前年の8月に秀吉の元を訪れた利休は、茶室を作るように命じられたという。半年ほどかけて、かの名高い茶室「待庵」を完成させたのである。
利休は秀吉によってひき立てられたというイメージがあるが、実際は織田政権の頃より秀吉と利休は親しかったようだ。信長は名物狩りを行ったので、頻繁に茶会を開いていたように思ってしまうが事実はそうではない。利休は、むしろ配下の武将たちとしきりに茶事を催していたのである。
秀吉もその1人であった。『宗及他会記』によると、天正7(1579)年4月22日利休は茶会において秀吉から贈られた円壺を用いているという。
また、天正9(1581)年6月12日には秀吉が茶会において利休より贈られた霰釜を小板に置いたとの記述が見える。この親密さは、1576年に秀吉が信長より茶会を催す事を許された以降に加速したものと思われる。
さて、この頃利休と秀吉はお互いをどのように思っていたのであろうか。
歴史学者の桑田忠親氏が著した『利休の書簡』に興味深い記述がある。利休の第三者への書状を見ると、1583年・1584年あたりの時期には「秀吉」と呼び捨てにしているものが多いというのだ。
どうもこの時期は、秀吉に対して臣従しているという意識が利休にはなかったようなのだ。織田政権時代には秀吉のほうが利休を「宗易公」と呼んでいたというのだから無理もない話である。
前述した待庵についても裏話がある。秀吉から建築を頼まれた利休は、薮内紹智宛、天正10(1582)年11月14日付書状にて「迷惑なることを頼まれた」と記している。次の天下人の最有力候補であろう秀吉に対して、この扱いは少々疑問である。
一方で、利休は本能寺の変後の天正10(1582)年6月15日付中川瀬兵衛尉清秀宛書状には驚かされる。その内容は、摂津茨木城主であった清秀の勝龍寺城での戦功を褒め称えるものであったからだ。これは明らかに一介の茶頭の立場を超えた内容の書状である。状況から見るに、この時点で利休は秀吉の側近として行動していることが窺える。
この一見すると矛盾する言動は何故であろうか。手がかりはやはり書状にあるようだ。
秀吉は天正13(1585)年7月に朝廷より関白に任じられる。その後は第三者への書状においても、秀吉を呼び捨てにすることがなくなり、関白様、殿下様になっていることが確認できる。
やっと臣従の意識が芽生えたともいえるが、秀吉の天下が不動のものになったことが大きいのではないかと私はにらんでいる。要は、1585年までは豊臣政権の確立を確信できず、あまり肩入れしている印象を周囲に与えたくなかったのではないだろうか。
一方の秀吉は側近としての利休に全幅の信頼をおいているように思える。このアンバランスが後の悲劇の背景にあるような気がしてならない。
利休切腹
実は「利休」という名は居士号であり、同年10月に秀吉が正親町天皇の禁中献茶を行うのに先立って宮中参内のため勅賜されたものである。ここにおいて、利休の「天下一の茶人」という地位は確立された。その後北野大茶湯を主管し、聚楽第の敷地に屋敷を構えたというから、その栄華は頂点を極めたといって良いであろう。
大坂城を訪れた大友宗麟は、豊臣秀長から「公儀のことは私に、内々のことは宗易(利休)に」とアドバイスされたという。利休は秀吉の政にも深く関与するようになっていたようだ。
ところが天正19(1591)年、利休は突然、秀吉の逆鱗に触れてしまう。
一説には、大徳寺山門上に建てられた利休の木像の下を通ることになった秀吉が激怒したことに端を発したという。あたかも利休が自分の頭を踏みつけているようだ、というのだ。その後、利休は堺に蟄居を命ぜられ、前田利家や弟子たちの助命嘆願も叶わず、切腹を命じられる。
これが通説におけることの顛末である。
しかし、私は昔からこの通説に疑問を持っていた。切腹に際して、弟子たちが利休を逃がす恐れがあるとして、秀吉が上杉景勝に軍勢で屋敷を囲むよう命じた、という記述を見つけたからだ。
これは、はっきり言って謀叛人に対する処遇である。そもそも大徳寺の利休像は利休が作らせたわけではない。つまり、切腹の理由が難癖としか言いようのないものなのだ。しかも、切腹と言いながら利休の首は一条戻橋に晒されたという点を見ると、罪人に近い方法で利休が葬り去られたとしか思えない。

秀吉がそこまでして利休を亡きものにしたかった理由は何だろう。これには実にたくさんの説が存在する。私が注目した説は、利休が徳川家康と共謀して秀吉を毒殺しようとしたため、という説だ。
ちなみに豊臣秀長毒殺説というのもあり、これについては以前秀長についての記事でも触れた。これも利休と家康の共謀となっているのは興味深い。
あわせて読みたい
いずれも、家康には何のお咎めもないことから信憑性に欠けるだろう。しかし、秀長の死後程なくして利休の蟄居、そして切腹が行われたことを考えると、あることが脳裏から離れない。
秀長の死の2日後に、利休と家康が2人きりで茶会を開いたという話である。秀吉がこの話を気にしたというか気に入らなかったということはないだろうか。
私がこのことに拘るのは、利休が本能寺の変の5日前に養子の小庵に送った手紙を読んだからである。そこには「信長様ご上洛との由、承った。(毛利攻めの最中の)秀吉殿はどうしておられるのか。分かり次第早急に連絡されたし」というような謎の記述があったのだ。
本能寺の変の前日に、信長が本能寺にて茶会を催したことは良く知られているが、この茶会の真の目的は博多の豪商鳥居宗室の所有する名物茶入れ「楢柴肩衝」を手に入れることであったらしい。
そして、この茶会をセッティングしたのが利休だったのである。重要なことは6月1~2日にかけて信長が確実に本能寺にいるということを利休は知っていたということである。
利休の情報網を駆使すれば、光秀がどのような動きをしているかなどすぐに判明したろう。利休の情報から、信長への謀反が起こる可能性があることを秀吉は掴んでいたのではないか。
実際、秀吉が本能寺の変が起こることをある程度予測していたという説が最近になって浮上してきている。つまり、利休は「中国大返し」のカラクリを知っていたというわけだ。
こんなことが家康などに知れたら厄介極まりないことは確かである。その家康に利休が近づき始めたと秀吉が邪推し始めたとしたらどうだろうか。そして、かつて信長から自分に乗り換えたように今度は家康に乗り換えようとしているなどと妄想を抱いたとしたら、利休が本当の謀反人に見えはしないか。
これが利休切腹事件に関する私の見立てである。
あとがき
ここまで書いてきて、利休は茶人という枠を超えたスケールの大きな人物であったと思わずにはいられない。茶の湯だけではなく、政治から軍事まで幅広い分野にその才能を発揮し、秀長とともに豊臣政権を支えた功績は大きい。私は徐々に、秀吉は利休を頼みにしながら一方では恐れていたのではないかという考えに傾きつつある。秀吉の心の闇はいつの頃からか豊臣政権を蝕み始めていたようだ。
【主な参考文献】
- 村井康彦 『千利休』 講談社学術文庫 2015 年
- 桑田忠親・小和田哲男監修 『千利休』宮帯出版社(改訂復刊)2011年
- 芳賀幸四郎 『千利休 』吉川弘文館 1986年
- 桑田忠親 『定本千利休の書簡 』東京堂出版 1971年
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
歴史にはまって早30年、還暦の歴オタライター。
平成バブルのおりにはディスコ通いならぬ古本屋通いにいそしみ、『ルイスフロイス日本史』、 『信長公記』、『甲陽軍鑑』等にはまる。
以降、バブルそっちのけで戦国時代、中でも織田信長にはまるあまり、 友人に向かって「マハラジャって何?」とのたまう有様に。 ...

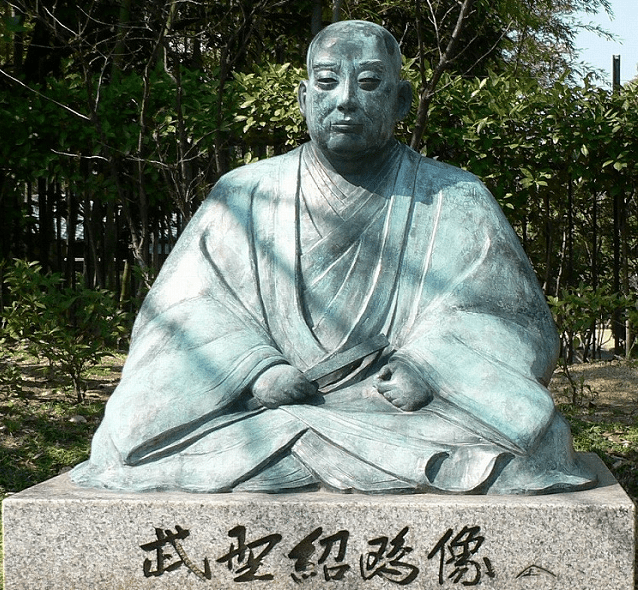

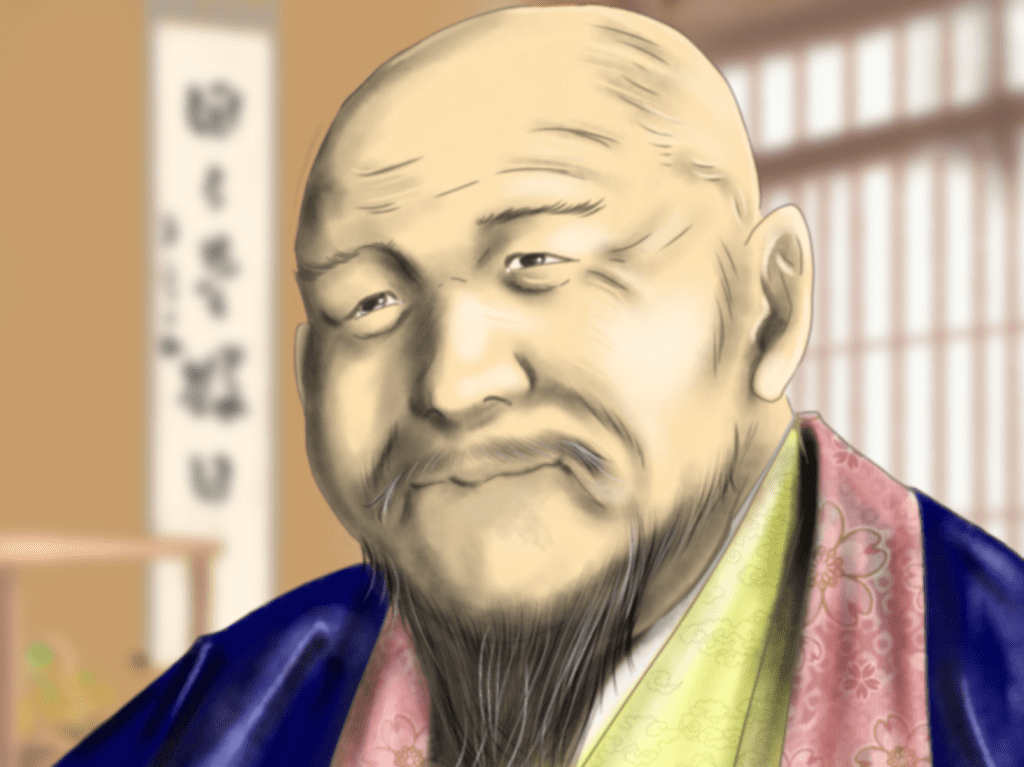


コメント欄