【悲運】イケメン使節団・遣唐使が挑んだ「地獄の航路」とその結末
- 2026/01/06

日本と大陸の国交は古く、その起源は卑弥呼の時代まで遡ります。以降、数多の王朝の興亡を経て交流は続き、密接な関係を築いてきました。今回は、命を賭して海を渡り、日本と唐を繋いだ「遣唐使」の実態に迫ります。
遣唐使第1号、犬上御田鍬の船出
遣唐使(入唐使)の初航海は舒明2年(630)、飛鳥時代中期のこと。前代の「隋」の滅亡を受け、遣隋使から遣唐使に名称を改めての再スタートでした。注目すべきはその選抜条件。実は遣唐使には「顔審査」がありました。日本を代表するに相応しい、イケメンな秀才たちが選ばれたのです。皇帝に謁見する以上、失礼がないように礼儀作法や立ち居振る舞い、学識も厳しくチェックされました。大使・副使が高級官僚クラスのエリートなのは当然として、各分野のトップが集結した点からも、当時の本気度が伝わりますね。
第1次遣唐使の大使に任じられた犬上御田鍬(いぬがみのみたすき)は、遣隋使の経験があり、百済の使節を無事に連れ帰った実績もある大和朝廷のベテラン外交官。そして共に渡った薬師恵日(くすしえにち)は日本に帰化した高句麗人。かつて第3次遣隋使では小野妹子に付き添って隋に渡り、最先端の医術を学んでいます。
彼らの派遣の目的は「貿易」と「学習」。当地の優れた技術や芸術、律令制度の知識や仏教の経典の持ち帰りは国家レベルの至上命題。当時の唐は、あらゆる面で日本の手本となる先進国だったのです。
「4隻に1隻」の生存確率
使節団は400~500人ほどで、4隻の船に分乗しました。1隻に100人前後が乗り込む計算ですが、航海は常に死と隣り合わせ。白雉4年(653)の第2次遣唐使では、各120人が2隻の船に乗り込んだものの、薩摩沖で1隻が難破し、高田根麻呂ら100名余りが死亡。生存者5人は板切れ一枚で1週間漂流した末、離島に打ち上げられ、疲労困憊の状態で筏(いかだ)を自作して都に帰還するという、凄まじいサバイバルを繰り広げました。分乗は「1隻でも辿り着けば儲けもの」という生存率を上げるための苦肉の策。天平勝宝4年(752)の第12次遣唐使では、首尾よく役目を果たしたのも束の間、帰路で立て続けに災難に遭遇します。藤原清河と阿倍仲麻呂の第1船が座礁して、安南(現在のベトナム中部)沿岸に漂着、現地人の襲撃を受けてほぼ全滅するという悲劇に見舞われたのです。
辛うじて難を逃れた2人は命からがら唐に戻り、再び皇帝に仕えることに。九死に一生を得た藤原清河は「河清」と改名し、結婚して娘・喜娘(きじょう)をもうけますが、帰国の夢は政情不安に阻まれます。
清河の叔母・光明皇后は、清河に宛てた歌で祈りを捧げます。
「大船に 真楫しじ貫き この吾子を 唐国にへ遣る 斎へ神たち」
(現代語訳:大きな船にたくさんの櫂(かじ)を並べ、準備を整えて、私の大切なこの子(清河)を唐の国へと送り出します。 どうか八百万の神々よ、この道中を、そしてこの子を、しっかりとお守りください。)
清河もまた、帰国まで梅が咲き続けるよう願う歌を返しました。しかし彼は再会を果たせぬまま客死。亡き父の代わりに連れてこられた娘の喜娘は、父の故郷の梅を見れたのでしょうか?
帰国を阻まれたのは皇帝玄宗に重用された阿倍仲麻呂も同様です。
「天の原 ふりさけ見れば春日なる 三笠の山にいでし月かも」
(現代語訳:(唐の地で)大空をはるか遠くまで見渡してみると、美しい月が昇っている。 かつて私の故郷・奈良の春日にある三笠山に昇った月と同じものなのだなあ。)
彼が詠んだ上記の歌は、唐土の月を故郷の月に重ねて懐かしむ歌です。『万葉集』収録作の中で唯一、外国で詠まれた歌として、今も人々の胸を打ちます。
日本は唐の属国と見なされていた
当時の外交は、皇帝に貢物を捧げ、返礼として宝物や官位を得る「朝貢貿易」が主流でした。本来、朝貢は皇帝に対して年1回行うしきたりでしたが、海を挟んだ日本は期間が空いても許されました。推古15年(607)の遣隋使・小野妹子が、聖徳太子に持たされた書簡「日出處天子致書日沒處天子無恙」のせいで皇帝の不興を買ったのも、このあたりの事情が関係しています。「天子」は中華を制す皇帝だけが使える称号なのに、属国の分際で名乗るとはけしからんというわけです。聡明な聖徳太子があえて「天子」と自称したのは、対等な外交を望む気持ちの表れでしょうか?
朝鮮・ベトナム・吐蕃(チベット)・新羅(朝鮮)・琉球も朝貢貿易の対象国であり、当時の唐がいかに影響力を誇っていたかが伺えます。遣唐使の献上品は絹や綿といった繊維の原材料に加え、干しアワビ・ナマコ・貝柱などの海産物。瑪瑙や銀などの宝石は勿論、『延喜式巻三十』に書かれた「海石榴油」こと椿油も喜ばれました。
対する皇帝の下賜品は、オリエンタルな絹織物や工芸品。乳製品や唐菓子、琵琶・笙・篳篥などの雅楽器や日用品の箸、二十四節気の暦も目録に含まれます。正倉院に収蔵されている「唐三彩」と呼ばれる美しい焼き物も遣唐使が持ち帰った物です。白菜・ピーマン・スイカも遣唐使の土産にあたり、長安の市場で入手した種が日本に持ち込まれました。
昔もあった、外国人留学生の不法滞在問題
遣唐船には勅命を帯びた官僚や貿易商の他に、多くの留学生や留学僧も同乗していました。用件が済み次第、帰国予定の役人たちと違い、彼らは唐に残留して学識を深めることが目的でした。衣食住に掛かる経費は国の負担になる上に、平均滞在期間は20年と長く、唐の政府は頭を悩ませていました。『旧唐書倭国伝』には、留学生の吉備真備が、唐朝から受けた特別手当てで本を買い漁り、意気揚々と帰国して行ったと記されています。こうした事態に唐側も対策を講じ、滞在期限を10年に短縮。延長希望者には自活を課しました。郷に入れば郷に従え、働かざるもの食うべからずです。阿倍仲麻呂が自ら科挙を受けて官吏になったのも、当初の滞在期限が切れたため、仕事を探していたという説が有力視されています。現代でいえば、正規のビザが失効し、不法滞在の身の上になった外国人のようなものですから、さぞ焦ったことでしょう。
仲麻呂と同じ第9次遣唐使に参加した井真成は、留学を中断して祖国に帰るのをよしとせず、最終的に唐の官吏となって36歳で亡くなりました。滞在期間17年。人生の半分近くを異国で過ごした彼の死に際し、皇帝は「尚衣奉御」の官位を贈り、手厚く弔ったそうです。
一方で、最澄と空海は延暦23年(804)の遣唐使に加わり、両名とも唐の高僧に師事し、山寺で修行を積みました。その後、空海は滋賀に比叡山延暦寺を建てて「天台宗」の開祖となり、空海は「真言宗」を教え広め、高野山に金剛峯寺を興しています。
仏に仕える身でなければ空海たちも働かねばならなかったことを考えると、知識や信仰心だけで腹は膨れない、シビアな現実が見えてきます。かと思えば6度の密航を企て、失明の代償を払って来日した鑑真のような唐人もいるので、信仰に命を懸けた人々のタフネスには驚かされるばかりですね。
おわりに
以上、遣唐使の歴史・実態をご紹介しました。日本代表として選ばれた「イケメン使節団」の運命は、まさに光と影が入り混じるものでした。死ぬまで帰国が叶わなかった者たちの胸中を思うとしんみりしますが、彼らが持ち帰った知識や文化は、今の日本の形を作る確かな礎となっています。
【参考文献】
- 東野治之『遣唐使』(岩波書店 2007年)
- 横田 肇『遣唐使と詩歌 その精神文化の背景を探る』(文藝春秋 2022年)
- 古瀬奈津子『遣唐使の見た中国』(吉川弘文館 2003年)
- 森 公章『遣唐使の光芒 東アジアの歴史の使者』(角川学芸出版 2010年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
読書好きな都内在住webライター。





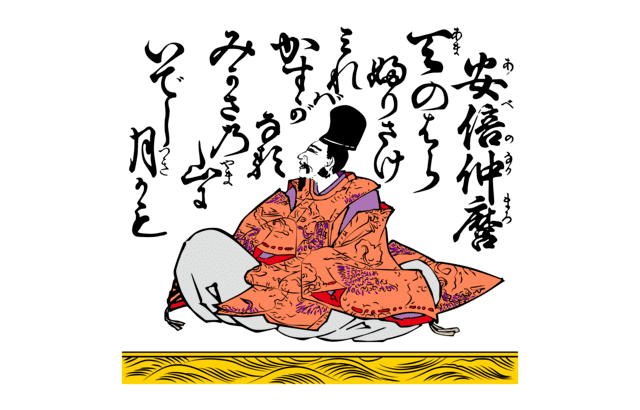


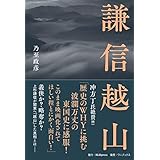





コメント欄