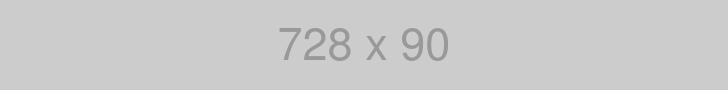
【小倉百人一首】7番・阿倍仲麻呂「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」
- 2022/12/19
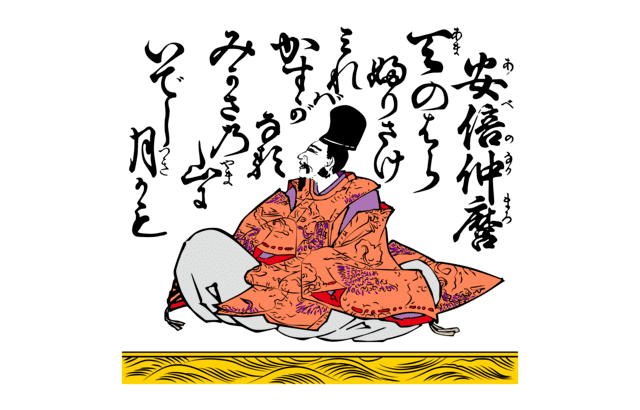
『小倉百人一首』7番歌は、百人一首の中では唯一外国で詠まれたとされている和歌です。遣唐使として入唐(にっとう)した阿倍仲麻呂(あべのなかまろ。氏は安倍、名前は仲麿の表記もあり)が、長年過ごした唐を離れて故郷へ帰る時、宴の席で詠んだといわれています。この和歌は確かに国へ帰りましたが、仲麻呂本人が故郷の地を踏むことはありませんでした。
【目次】
原文と現代語訳
【原文】
天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも
【現代語訳】
(唐の地で)大空を振り仰ぎはるか遠くを見ると月が見えるけれど、あの月は奈良の春日にある三笠山に出ていた月と同じ月なのかなあ。
歌の解説
天の原
広々とした大空。ふりさけ見れば
「ふりさけ見る」は、振り仰いで遠方を見ること。「天の原ふりさけ見れば」という表現はこの歌に限らず『萬葉集』に見られ、「安麻能波良(アマノハラ)ふりさけ見れば夜そふけにけるよしゑやし一人寝る夜は明けば明けぬとも(遣新羅使人)」や、「安麻乃波良(アマノハラ)ふりさけ見つつ 言ひ継ぎにすれ(大伴家持)」などがあります。また、「振り返って月を見る」表現で有名な歌に、こちらも『萬葉集』に収録されている「東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ(柿本人麻呂)」があります。
春日なる
「なる」は、前に地名がつくため存在の助動詞「なり」の連体形で、「春日にある」という意味。春日は地名で、現在の奈良市春日野町あたり。藤原氏の氏神である春日大社が有名です。三笠の山
春日大社の後方にある山で、現在は「御笠山」「御蓋山」ともいいます。若草山、高円山(たかまどやま)と並ぶ山で、このうち若草山も別名を「三笠山」といいます。出でし月かも
動詞「出づ」に過去の助動詞「き」の連体形「し」がついて、「出ていた」という意味になります。「かも」というのは上代に使われていた疑問の意味を含む詠嘆の終助詞です。作者・阿倍仲麻呂
阿倍氏は『日本書紀』によれば、孝元天皇(こうげんてんのう)の皇子・大彦命(おおひこのみこと)を祖とし、『古事記』によれば、大彦命の子・建沼河別命 (たけぬなかわわけのみこと)を祖とする古代の豪族です。大化の改新(乙巳の変)のときの阿倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)は左大臣にまでなった名族でした。仲麻呂はというと、中務大輔(なかつかさたいふ)の阿倍舩守(ふなもり)の子として698年に生まれたとされ、養老元年(717)に遣唐留学生として唐へ渡りました。同じ時に入唐した人に吉備真備(きびのまきび)がいます。真備はのちに帰国して故郷の朝廷で大出世しましたが、仲麻呂は一度唐へ渡って以来、二度と故郷に戻ることはできませんでした。
唐で仲麻呂は玄宗皇帝に重用され、朝廷では朝衡(ちょうこう)と名乗って高官に昇っています。その中で、有名な詩人の李白や王維らとも親交を深めていたようです。
仲麻呂は一度も故郷に戻らなかった、と紹介しましたが、戻ろうとしなかったわけではありません。唐で出世したいと帰国を見送ったこともありましたが、一度帰国を決意して船で故郷をめざしたこともありました。それが天平勝宝5年(753)のこと。
実はこの時期、日本に正しい仏教を広めるべく、唐僧の鑑真を渡日させようという一大プロジェクトが動いていたころで、仲麻呂も鑑真渡日計画に関わっていました。仲麻呂は遣唐大使の藤原清河(ふじわらのきよかわ)とともに、鑑真を渡日させるべく帰国することになったのです。仲麻呂は10代後半で故郷を離れ、すでに30数年を唐の地で過ごしていました。
その帰国の途に詠んだといわれているのが、「天の原……」の和歌でした。『古今和歌集』巻第9「羇旅歌(きりょのうた)」の最初にこの和歌が載っています。詞書は「唐土にて月をみてよみける」とあり、和歌本文の後ろには注が添えられています。
それによれば、仲麻呂は帰国のため出発したあと、明州の海岸で唐の人々が送別会を開いてくれ、その夜月を眺めながら歌を詠んだ、ということです。この記述をそのまま鵜呑みにすることはできませんが、本当だとしたら、仲麻呂はいよいよ帰国がかなうというタイミングで、「この月は故郷の三笠山で見た月と同じなんだなあ」と、ふと故郷を身近に感じたのかもしれません。
しかし、結局仲麻呂が国へ戻ることはかないませんでした。仲麻呂が乗った船は悪天候により難破し、現在のベトナムに漂着しました。仲麻呂は再び長安へ戻って唐朝に仕えることになりました。一方、別の船に乗っていた鑑真は過去数度日本へ渡ろうとして失敗し、失明までしましたが、今回はついに上陸に成功しています。
帰国を諦めた仲麻呂は、唐朝で秘書監、左補闕となり、やがて皇帝のそばに侍る側近の左散騎常侍、都護府の長官の鎮安南都護に抜擢され、大暦5年・宝亀元年(770)に70代半ばで生涯を閉じました。その功績により、唐朝から潞州大都督の称号が贈られています。
本当に仲麻呂が詠んだ和歌?
故郷へ帰る帰途に詠んだとはいえ、仲麻呂本人は戻ってこなかったわけで、この和歌がどうやって日本に伝えられたのか、そもそも和歌だったのか、という疑問が残ります。一緒に帰国する遣唐使が仲麻呂の詠んだ歌を記録していて、別の船に乗って無事帰国して伝えたと考えることもできるかもしれません。ただ、この歌がどんなふうに伝わったかはよくわかっていません。そもそも仲麻呂は和歌として詠んだのでしょうか?
使われている言葉や表現を見ると確かに万葉時代の和歌の雰囲気もあるのですが、実はもともと漢詩で詠まれていて、のちの時代に誰かが和歌に翻案したのではないか、という説があります。
では誰が翻案したかというと、有力視されているのが『古今和歌集』の撰者のひとり紀貫之(きのつらゆき)です。本当かどうかはわかりません。
その貫之は、『土佐日記(土左日記)』の中で仲麻呂とこの和歌について記しています。そこには仲麻呂が唐の人々に「わが国ではこのように歌を詠むのです」といって「天の原……」の和歌を詠んだ(※『土佐日記』は初句を「青海原(あをうなばら)」とする)と記していますが、本当はどのように詠まれた歌だったのでしょうか。
おわりに
仲麻呂は一度帰国をめざしながら、なぜ唐に留まることを選んだのか。仲麻呂にとってはすでに唐で過ごした時間のほうが長く、帰国の決断もかなり勇気のいることだったはずです。年齢もとうに50を超えていて、何かと危険の伴う船旅は厳しい。それよりも、残りどれくらいあるかわからない短い人生をこの地(唐)で終えよう、そう思ったのかもしれません。帰国を諦めた仲麻呂を思うと、より一層切なく感じられるような、「二度と戻れない故郷だけど、同じ月が輝いている」と感じられる仲麻呂の感性に救われるような、そんな和歌でした。
【主な参考文献】
- 『日本国語大辞典』(小学館)
- 『小学館 全文全訳古語辞典』(小学館)
- 『国史大辞典』(吉川弘文館)
- 『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)
- 『世界大百科事典』(平凡社)
- 吉海直人『読んで楽しむ百人一首』(角川書店、2017年)
- 冷泉貴実子監修・(財)小倉百人一首文化財団協力『もっと知りたい 京都小倉百人一首』(京都新聞出版センター、2006年)
- 目崎徳衛『百人一首の作者たち』(角川ソフィア文庫、2005年)
- 校注・訳:小沢正夫・松田成穂『新編日本古典文学全集11 古今和歌集』(小学館、1994年)
- 校注・訳:菊地靖彦『新編日本古典文学全集13 土佐日記/蜻蛉日記』(小学館、1995年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
大学院で日本古典文学を専門に研究した経歴をもつ、中国地方出身のフリーライター。
卒業後は日本文化や歴史の専門知識を生かし、 当サイトでの寄稿記事のほか、歴史に関する書籍の執筆などにも携わっている。
当サイトでは出身地のアドバンテージを活かし、主に毛利元就など中国エリアで活躍していた戦国武将たちを ...









コメント欄