「源頼家」鎌倉幕府第2代将軍。暗君か、それとも悲劇の将軍か
- 2022/06/23

鎌倉幕府を開いた源頼朝亡き後、第2代将軍に就任したのは嫡男の源頼家(みなもと の よりいえ)です。
18歳の若さで鎌倉殿となった頼家の独裁に御家人たちは不満を抱きました。実権を奪われた頼家は側近を特別待遇で扱ったり、御家人の妾に手を出したり、蹴鞠・鷹狩といった趣味に耽溺するなど、享楽に耽るように。
そのような姿から頼家は暗君と評価されることが多いですが、鎌倉幕府草創期の不安定な状況下で父・頼朝が思いがけず早く亡くなってしまったこと、頼家自身若すぎたことなど、不運な条件が重なってしまったことも考慮する必要があるでしょう。
18歳の若さで鎌倉殿となった頼家の独裁に御家人たちは不満を抱きました。実権を奪われた頼家は側近を特別待遇で扱ったり、御家人の妾に手を出したり、蹴鞠・鷹狩といった趣味に耽溺するなど、享楽に耽るように。
そのような姿から頼家は暗君と評価されることが多いですが、鎌倉幕府草創期の不安定な状況下で父・頼朝が思いがけず早く亡くなってしまったこと、頼家自身若すぎたことなど、不運な条件が重なってしまったことも考慮する必要があるでしょう。
源頼朝嫡男として
源頼家は、源平の争乱の真っただ中の寿永元(1182)年8月12日に生まれました。幼名を万寿(または十万)といいます。父・頼朝にとっては待望の男子誕生でした。頼朝は河越重頼室(比企尼の娘・比企能員の妹)、平賀義信室(比企尼の娘)らを乳母にし、比企能員や平賀義信を乳母夫にしました。頼朝は比企尼の一族に頼家の養育を任せたのです。
富士の巻狩
頼朝は頼家を自分の後継者にするべく、源氏の棟梁として恥ずかしくない武士に育てました。平安時代末期ごろの武士といえば、儀式で弓馬の芸を披露できるだけの技術をもっていて、戦場のマナーを身につけているものです。しかし治承・寿永の内乱で源氏が集めた者の中には、その定義には当てはまらないアマチュアレベルの武士たちが多かったようです。御家人もその例にもれません。
『平家物語』は「滅びの美学」の代表といわれますが、平氏一門は武士の伝統とマナーを守って戦い、源氏は当時の常識を破る戦い方をしたためにあのような結果になった、という見方もあります。
頼朝は頼家の教育を通じて、御家人たちの武士としてのレベルをも上昇させたかったのかもしれません。秀郷流故実を継承する下河辺行平を頼家の師範にて訓練させました。そのおかげもあって、頼家は武家の棟梁にふさわしい確かな技術を身につけていきました。
建久4(1193)年5月、頼朝は駿河国富士の巻狩(狩場の四方を取り囲んで獣を追い込み狩りをする方法)を開催し、頼家の武芸を披露しました。この時12歳の頼家は見事に鹿を射て頼朝を喜ばせています。『吾妻鏡』によれば頼朝はこの喜びを政子にも伝えましたが、政子は「そんなことで使いをよこすな」という態度で、両親の反応はまったく違っていたようです。
思い通りにいかない2代目の不満
建久10(1199)年正月13日、頼朝が亡くなりました。それは出家した二日後のことで、12月27日に体調を崩してからずいぶん慌ただしく、急死であったことがうかがえます。その後、朝廷に頼朝の遺領継承が認められると、頼家は左近衛中将、そして第2代将軍へ。さらに翌年には従三位左衛門督になりました。
十三人の合議制
正治元(1199)年4月、「十三人の合議制」と呼ばれる体制が成立しました。メンバーは以下のとおりです。北条時政、北条義時、大江広元、三善康信、中原親能、三浦義澄、八田知家、和田義盛、比企能員、安達盛長、足立遠元、梶原景時、二階堂行政
これはよく頼家が訴訟を取り上げて裁断を下すことを禁じ、13人の宿老の合議によって決められることになったと解釈されますが、別の見方もされています。
吉川本『吾妻鏡』には、頼家が13人以外から直接訴訟を聞き届ける「聴断」を否定したとあり、頼家が一切訴訟に関わらないこと、つまり親裁権を否定するものではないということです。
しかし、頼朝時代に比べて制約があることに違いはありません。頼家がもともとどう考えていたかはわかりませんが、父・頼朝と同じように将軍独裁政治でやっていこうと考えていたならば、納得がいかない展開だったでしょう。
事実、頼家はこの13人の合議制に反発するように、比企宗員、比企時員、小笠原長経、中野能成以下5人の近侍を重用しました。彼らが鎌倉で狼藉に及んでも訴えてはならないという通達を政所に伝え、また彼ら以外は特別の場合を除いて頼家との面会を許さないと命じたのです。
また同年7月、頼家は安達景盛(盛長の嫡男)の妾に目を付け、景盛が三河国に赴いて留守にしている間にその妾を連れ出して奪いました。さらに帰ってきた景盛がこれに憤慨すると、今度は景盛を討とうしたのです。政子が景盛をかばい頼家を諫めたことで事なきを得ますが、家臣の妾を奪った挙句家臣を殺そうとするとは、とても人の上に立つ者がすることとは思えない所業です。
梶原景時の変
同年10月、御家人66名から景時を弾劾する連判状が提出されました。事の起こりは政子の妹・阿波局の告げ口です。御家人の結城朝光が「忠臣は二君に仕えずという」と頼朝時代を懐かしんで代替わりした時に出家すべきだったと発言したことを、景時は「頼家への謀反のあらわれだから討つべきだ」と頼家に讒言しました。阿波局はそれを聞いていて、「あなた、殺されるみたいですよ」と朝光に伝えたのです。
それを信じた朝光が三浦義村に相談し、そこから景時弾劾へと進んだのです。頼家が弁明を求めたものの景時は申し開きをせず、一族を引き連れて鎌倉を出ました。そして、翌正治2(1200)年正月20日、景時は京へ向かう道中で討伐に向かった御家人に討ち取られ、一族は滅亡しました。
この一件について、天台宗僧侶・慈円が「景時をかばいきれなかったことが頼家最大の失敗だ」と『愚管抄』に記しています。つまり、これがきっかけで頼家は失脚することになったというのです。
景時は頼朝の寵臣で、上総介広常や源義経を讒言して粛清させたといわれる人物です。頼朝は景時の有能さと性格の激しさで周りに嫌われ問題を起こす一面を理解しながらうまく使っていましたが、頼家はそれができなかったのでしょう。その結果、景時を見捨てるような形になってしまったのです。
あわせて読みたい
蹴鞠に熱中する頼家
蹴鞠といえば、蹴鞠好きで家を滅ぼしたボンクラ息子という評価がある今川氏真を思い出しますが、頼家にも共通するものを感じます。蹴鞠に夢中だから暗愚なのか、それとも偉大過ぎる父のせいでそう見えるだけなのか……。蹴鞠に耽る頼家は、諸国が飢饉に見舞われてもお構いなしに楽しみました。そんな息子を政子は度々諫めながらも、建仁2(1202)年6月に頼家の蹴鞠を見物するなど、一応趣味を理解する姿勢を見せたようです。
内乱勃発
同年7月22日、頼家は従二位に叙され、征夷大将軍に任ぜられました。しかし頼家の時代は長く続かず、翌建仁3(1203)年秋にはその地位を失うことになりました。阿野全成の失脚と比企氏の乱
梶原景時の失脚後に勃発したのが、北条氏と比企氏の争いです。比企氏は冒頭で紹介したように頼家の養育に関わった一族。また、比企能員の娘・若狭局は頼家の妻で、ふたりの間には一幡という男子がいました。
妻と子を通じて比企氏との結びつきを強める頼家に、千幡(のちの実朝)の乳母である阿波局とその夫で乳母夫の阿野全成(頼朝の弟)が危機感をもつのは無理もないことです。さらに、そこに北条時政が絡んできます。このまま比企氏を外戚にもつ一幡が頼家の後継者になれば、時政は将軍の外戚としての立場を失ってしまうのです。
建仁3(1203)年5月19日、頼家は全成を謀反の疑いで捕らえました。全成は常陸国に流され、誅殺されてしまいました。妻の阿波局も捕らえられるはずでしたが、姉・政子の拒否と弁明により助けられています。ちなみに、全成の失脚したことにより時政が千幡の新しい乳母夫に就くことになりました。
もともと病弱だった頼家は、同年7月に急病で倒れてしまいます。8月には余命わずかといわれ、27日に家督継承の評定が開かれました。そこでは「一幡に関東28か国の地頭職と惣守護職を譲ること」「千幡に関西38か国の地頭職を譲ること」が決められています。
そんな中、9月2日に事件が起こりました。比企一族が滅ぼされてしまったのです。『吾妻鏡』によれば、頼家の寝所で頼家と能員が時政討伐の密談をしていて、それを障子越しに聞いていた政子が時政に知らせたため、時政は殺される前にと能員を殺害した、という経緯のようです。ちなみに一幡はこの一件で亡くなったとも、生き残ったともいわれます。
『吾妻鏡』を信じるならば時政の正当防衛と言えなくもありませんが、『愚管抄』は時政が能員を暗殺したと伝えています。先に相手を手にかけようとしたのが能員なのか時政なのか、実際のところはよくわかりません。政子の盗み聞きによりことが動き出すというのは梶原景時の変の阿波局の例と似ていて、なんだかどちらも盗み聞きしたというのは作り話なのでは、と疑ってしまいます。
この後危篤を脱した頼家は激しく怒り、堀親家を使者に和田義盛と仁田忠常に時政を討つように命じますが、義盛はそれを時政に知らせてしまいました。結局何の罪もない使いの親家が時政に殺されてこの一件は終わりました。
幽閉、暗殺される
比企氏を失った頼家は9月に政子の勧めにより出家させられ、修禅寺に幽閉されてしまいました。同時に家督は実朝(千幡)へ移ります。将軍就任からまだ1年余りのことでした。翌元久元(1204)年7月18日、頼家は修禅寺で亡くなりました。北条氏が差し向けた討手に殺されたといわれています。『愚管抄』には、入浴中に襲撃されかなり抵抗したという頼家のむごたらしい最期が記されています。
頼家の評価
頼朝は亡くなるまで北条氏と比企氏の結合に力を入れていたようですが、それが完成する前に思いがけず急死してしまい、結果両者は対立することになりました。頼家はそれに巻き込まれる形で地位を失ったといってもいいでしょう。頼朝の妻の家である北条氏と、流人時代から支えてくれた比企尼の比企氏。頼家の養育を比企氏に託したのも頼朝です。その時はこのような対立を生むとはゆめにも思っていなかったでしょう。また、平氏打倒という大きな目的のために集まった人々はその間は結束していても、平和になってから内部に新たな敵を見出すというのはままあることでしょう。不安定な幕府草創期に頼朝が亡くなってしまったというタイミングの悪さが、頼家の不運でした。
頼家は、立派な武家の棟梁になるべく育てられ、確かに幼いころはそれにふさわしい優秀な人物であったことがうかがえます。代替わり当初も、張り切って父と同じように自分が先頭に立って政治を行おうとしたのではないでしょうか。それが宿老たちに押さえつけられ、ポッキリ折れてしまったのです。
そもそも、頼家=暗君というイメージは『吾妻鏡』によってつくられたものである可能性もあります。『吾妻鏡』が北条氏の周辺で編纂されたことを考えると、源氏3代ののちの北条氏の執権政治の正当性を前面に出すために、頼家に武家の棟梁としての能力がないかのように編集されたのかもしれません。
それにしても、歴史にもしもはありませんが、頼朝がもう少し長生きして周囲を整え、北条氏と比企氏の結合も完成していれば、頼家ももっと違った形で力を発揮できていたかもしれないと思います。
【主な参考文献】
- 『国史大辞典』(吉川弘文館)
- 岡田清一『北条義時 これ運命の縮まるべき端か』(ミネルヴァ書房、2019年)
- 永井晋『鎌倉幕府の転換点 『吾妻鏡』を読みなおす』(吉川弘文館、2019年)
- 元木泰雄『源頼朝 武家政治の創始者』(中央公論新社、2019年)
- 渡辺保『北条政子』(吉川弘文館、1961年 ※新装版1985年)
- 『国史大系 吾妻鏡(新訂増補 普及版)』(吉川弘文館)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
大学院で日本古典文学を専門に研究した経歴をもつ、中国地方出身のフリーライター。
卒業後は日本文化や歴史の専門知識を生かし、 当サイトでの寄稿記事のほか、歴史に関する書籍の執筆などにも携わっている。
当サイトでは出身地のアドバンテージを活かし、主に毛利元就など中国エリアで活躍していた戦国武将たちを ...





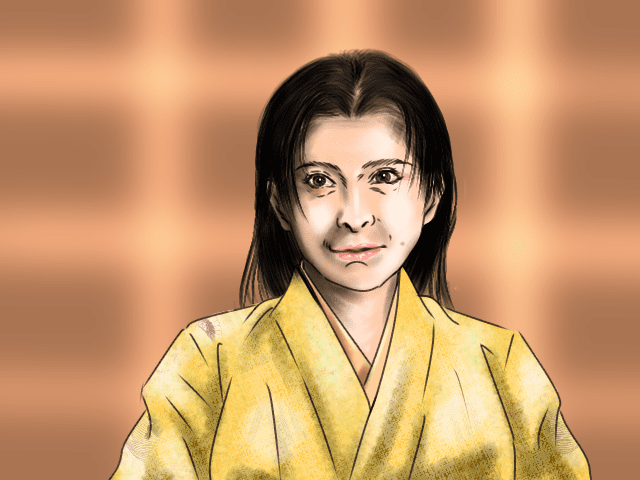
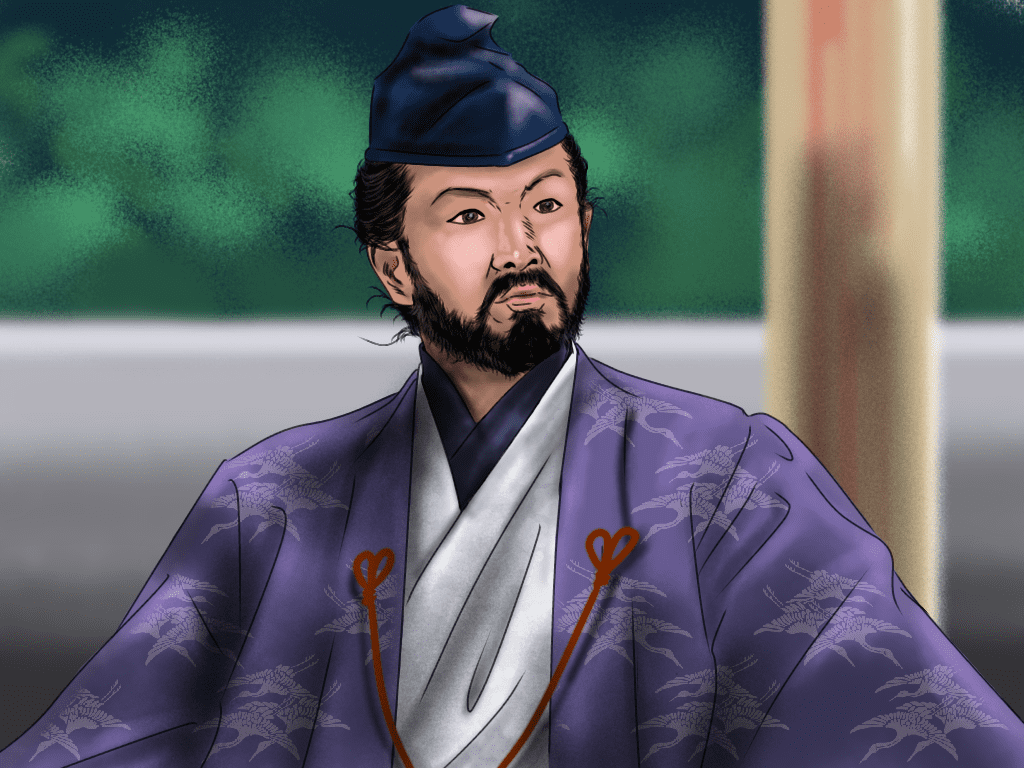

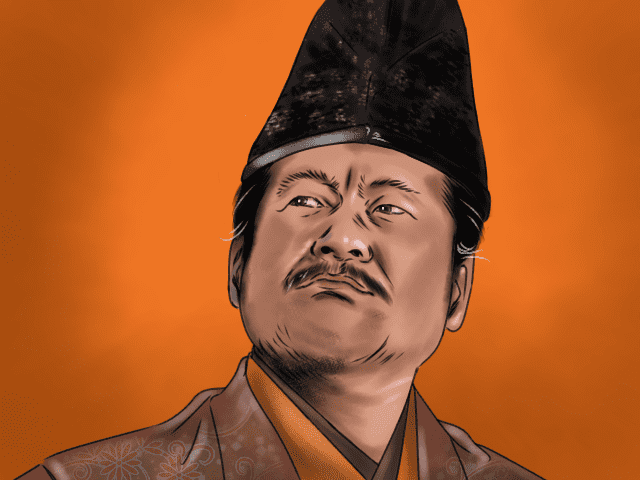






コメント欄