常に死と隣り合わせの戦国武将が追い求めた「滅びの美学」とは?
- 2024/04/30
渡邊大門
:歴史学者

勝利こそ重要だった
戦国武将は絶えざる戦いのなかで、常に死と隣り合わせにあった。「滅びの美学」とは、そうした中で形作られたものである。最初に、戦国武将の死生観について、触れておくことにしよう。戦国武将にとって、合戦で敵対する武将に勝利することがすべてだった。朝倉氏の家臣だった朝倉宗滴の書『朝倉宗滴話記』(16世紀中後半成立)に有名な一節がある。
「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」
文字通り、武士は勝つことが本質であるということだ。武士を犬畜生に例えているが、それでも勝つことが大事だと言うのである。
同じく江戸時代初期に編纂された軍学書『甲陽軍鑑』には、
「国持大将、人の国をうば(奪)ひとり給ふこと、国に罪はなけれども、武士の道たる故にや」
と書かれている。国持大将、つまり戦国大名たる者は、他国に侵攻して国を奪うことが本質だというのである。

このように戦国武将は絶えざる戦いのなかで勝利し、領土を拡張することが本質的な存在意義だったといえる。逆に言えば、敗北は死を意味したといえよう。
いずれにしても、命懸けだったのは事実である。実際、敗者は悲惨な最期を迎えることが多かった。
死への意識
勝利以外に道がない戦国武将は、常に死を意識していた。『甲陽軍鑑』には、「戦場に於いて、聊か未練をなすべからず事。呉子に曰く、生を必ずするときんば死す。死を必ずするときんば生く」
という有名な一節がある。文中の『呉子』とは中国の兵法書で、「武経七書」の一つである。
内容を簡単に述べておくと、「戦場で生きようとすると死ぬが、死を覚悟すると生きることができる」という意味になる。つまり、いったん戦場に出て逃げ回って生きようとするよりも、死を覚悟して立ち振る舞ったほうがよいということなのだ。戦国武将は国を奪うという「利」を求める一方、常に「死」を意識し、向き合っていたのである。
義の精神の重要性
戦国武将のなかには、戦いに「義」の精神を求める者もあった。小田原北条氏五代の歴史を描いた『北条記』には、次のように書かれている。「昔は義の為に命を失ひ名を揚しに、今又欲の為に義をうし(失)なひ名をけか(汚)す。是をも少も思はす。唯人の国をと(取)らんとのみはか(謀)る。浅ましきとも愚かなり」
「昔は義の為に命を失い、名を上げたものだが、今は欲の為に義を失い名を汚すありさまだ。こういうことを少しも考えず、ただ人の国を奪おうと謀略を練る。浅ましく愚かなことである」という意になろう。まさしく戦国武将の美学であり、私利私欲で戦うことを諌めている。
戦国武将は戦いに勝つことがすべてであると述べてきたが、ここでは「義」が尊重され、「義」なくして国を奪おうとすることは愚かであると断じる。つまり、「利」を求めて戦うことと、一線を画しているのだ。
「義」を重んじた武将としては、上杉謙信が有名であろう。『謙信家記』では、盛んに義の重要性が説かれている。その中で重要なのは、「義」のために戦ったのであれば勝敗は二の次で、武士の面目は保持されるという考え方である。戦いは国を奪う「利」では測ることができず、「義」が重んじられる側面もあった。

命懸けの忠誠心
主に仕える家臣には、命を捨てるくらいの忠誠心があったことも重要である。江戸時代初期に大久保彦左衛門忠教が子孫に書き残した『三河物語』に、よく知られたくだりがある。「此君にハ妻子を顧みず、一命ヲ捨テ屍ヲ土上ニサラシ、山野ノケダ物ニ引チラサルゝトテモ、何カハ惜シカランヤ」
「この主(徳川家康)の為なら妻子を顧みず、一命を捨てて屍を野に晒し、たとえ山野の獣に死骸を食いちぎられても命は惜しくない」という意になる。これこそが「家康の為ならば、命を捨てても惜しくない」という三河武士の真骨頂であろう。また、『三河物語』には「追腹」つまり殉死にも触れているが、主君と家臣の一体化を説き、主君の為なら死をも辞さない覚悟が説かれている。
ここに拠った史料はおおむね近世に成立したものであるが、それぞれの戦国武将の死生観が詳しく描かれており、大変興味深い。それは、戦国武将の「滅びの美学」に通じるものがあるのではないか。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
1967年神奈川県生まれ。千葉県市川市在住。関西学院大学文学部史学科卒業。佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現在、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役。日本中近世史の研究を行いながら、執筆や講演に従事する。主要著書に『誤解だらけの徳川家康』幻冬舎新書(新刊)、 『豊臣五奉行と家 ...







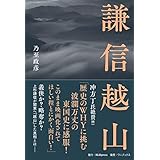




コメント欄