歌舞伎や『大岡政談』にも登場! 天一坊は本当に将軍・徳川吉宗の御落胤だったのか?
- 2024/03/01

第8代将軍・徳川吉宗の時代、江戸に吉宗の御落胤と称する1人の若者が現われる。天一坊(てんいちぼう)と名乗った彼は、父・吉宗との面会を願う。
この事件は名奉行・大岡越前守忠相の活躍を記した『大岡政談』として、また歌舞伎の演目としても有名である。時代物のドラマでもたびたび取り上げられるこの出来事は、大変ドラマティックで面白い筋書きなのだが…。
今回は、江戸の有名事件としても取り上げられることの多い、いわゆる「天一坊事件」について、その真偽のほどを探ってみたい。
この事件は名奉行・大岡越前守忠相の活躍を記した『大岡政談』として、また歌舞伎の演目としても有名である。時代物のドラマでもたびたび取り上げられるこの出来事は、大変ドラマティックで面白い筋書きなのだが…。
今回は、江戸の有名事件としても取り上げられることの多い、いわゆる「天一坊事件」について、その真偽のほどを探ってみたい。
『大岡政談』とは
『大岡政談』とは、吉宗の時代に活躍した江戸町奉行・大岡忠相が解決した数々の事件が記されたものとされている。
しかし、これは大岡忠相が亡くなったあとに著されており、ほとんどが創作だと言われている。その『大岡政談』の中で最も有名なのが、今回紹介する「天一坊事件」である。
江戸末期には河竹黙阿弥が脚色した歌舞伎が大人気となり、講談として興行されることもあった。『大岡政談』に書かれている天一坊事件の概要は次の通りである。
『大岡政談』に書かれた天一坊事件
1、突然現れた吉宗御落胤
ある日、江戸の町に突然、吉宗の御落胤を名乗る天一坊という青年が現われ、父である吉宗との対面を願い出る。江戸城内では、天一坊の正体をめぐって大騒ぎとなる。実は、天一坊が主張していた吉宗の御落胤とは真っ赤な嘘であった。
2、紀州時代の吉宗と、腰元・沢の井
吉宗がまだ紀州藩にいて、徳太郎と名乗っていたころ、吉宗の身の回りの世話をする「沢の井」という腰元がいた。沢の井は吉宗のお手付きとなり、子供を宿す。※ 腰元(こしもと)
上流の商家の人々の側に仕えて雑用をたす侍女(小間使(こまづかい))をさし、身の回りにおいて使うことから腰元使ともいう。
(出典:コトバンク)
吉宗は兄がいたために紀州藩を継げる身分ではない。しかし、そこは名門徳川紀州藩直系の子である。さすがに腰元を正妻にすることは難しい。厳しい身分制度の中、沢の井は泣く泣く宿下がりをするが、その際吉宗は、家康からもらった短剣とお腹の子が自分の子であるというお墨付きを沢の井に渡した。
実母・お三のもとに帰った沢の井は、やがて男の子を産み落とすが、その子は生まれてすぐに亡くなってしまう。そして子どもの後を追うように沢の井も亡くなった。

3、僧侶の悪だくみ
一度に娘と孫を失ったお三は、悲しみのあまり正気を無くすが、ことあるごとに娘が紀州の殿様との間に子供を授かったと話していた。これを聞いたのが宝沢(ほうたく)という若い僧侶であった。宝沢は、短剣を売りさばこうと企み、お三を殺害し、短剣とお墨付きを奪って逃亡するが、すぐに短剣を売ることはなかった。

4、御落胤・天一坊の誕生
数年後、徳太郎が8代将軍吉宗となったことで、宝沢はある計画を立てる。逃亡途中で知り合った赤川大膳(あかがわたいぜん)や山内伊賀亮(やまのうちいがのすけ)らと共に、計画は具体的な筋書きとなり、宝沢は吉宗の御落胤・徳川天一坊を名乗る。
5、天一坊の吟味
各所で吉宗の御落胤と名乗った天一坊が江戸へ出てくるころには、仕官を望む多くの浪人を従えて、江戸っ子の注目となる。あまりの騒ぎに幕府としても無視できない。そこで、天一坊が老中・松平伊豆守の役宅に呼び出され、御落胤の真偽を確かめることとなる。しかし短剣やお墨付きといった動かぬ証拠があるばかりでなく、短剣を見せられた吉宗も「心当たりがある」というのだ。
これは御落胤に間違いない…。皆がそう思い始めたところ、大岡忠相ただ1人が疑惑の目を向けるのである。

6、覚悟の忠相
忠相たっての願いとして、再度天一坊の吟味を行うが、やはり御落胤であることを認めざるを得ない状況となる。そこで忠相は家来を密かに紀州へ走らせた。忠相は、天一坊の素性を晴らすための時間を稼ぐため、自らは切腹し、あとを家臣に任せる覚悟をした。7、天一坊と一味の最期
忠相が今まさに切腹しようというそのとき、家来が紀州から帰って来る。そして、沢の井とその子の死を確認してきた家来により、天一坊の偽証が明らかとなった。天一坊とその仲間は、御落胤を詐称し、浪人を集めて世間を騒がせた罪で打ち首獄門となった。

魅力的な筋書きが人気となった天一坊事件
歌舞伎では、忠相と天一坊の参謀である山内が対決するシーンや、忠相が妻子とともに白装束となって切腹しようとする場面が見せ場となっているが、もちろんこんなドラマティックな史実はなかった。天一坊の吟味に役宅を提供した松平伊豆守は、3代将軍家光の時代に活躍した人物であり、吉宗の時代に生きているわけがない。知恵伊豆と言われるほどの切れ者であったという松平伊豆守を登場させることで、より劇的な事件として演出したのではないだろうか。
こうして、時代劇や歌舞伎ファンにとって、天一坊事件は大変魅力的で興味深いドラマとなった。
史実としての天一坊事件
『大岡政談』に登場した天一坊のモデルと考えられているのが、天一坊改行という山伏である。源氏坊改行とも呼ばれるこの人物の母親・よしが一時紀州家に奉公していたことは確からしい。となると、その時に吉宗の手が付いたという可能性もゼロではない。
強運に恵まれた吉宗
そもそも吉宗という人は、紀州徳川家第2代藩主・光貞の四男として生まれており、到底紀州藩の後継ぎになる見込みはなかった。その上、母の身分が低かったため、冷遇されていたそうだ。このまま一生部屋住みとして生きていくしかなかった吉宗が、相次ぐ兄の死により、紀州藩を相続することとなる。そして、将軍継嗣候補までもが相次いで亡くなったため、吉宗はめでたく(?)8代将軍となった。まさに棚ぼた将軍!強運にもほどがある。ちなみに、吉宗の兄や将軍継嗣の死については毒殺説もある。
吉宗には覚えがあった!
若い頃は、藩主、ましてや将軍になるなど考えられない立場だった吉宗は、元来壮健で、女性関係もお盛んだったらしく、自由気ままに過ごしていたのだろう。そんな中で、城中の女性についつい手を付けることもあったようだ。吉宗自身が、よしという女性と関係があったかどうか、改行が御落胤であるかどうかについて、「覚えがある」と言ったというのもうなずける。よし以外にも「覚えがある」女性はいたのかもしれない。
なぜ天一坊は自分を御落胤と思ったのか
改行は幼い頃に母を亡くしている。その母が生前、改行に「吉」の字を大切にするように言っていたらしい。また、母が亡くなったとき、改行は伯父から「いずれ公儀(=将軍家や幕府を指す)からお尋ねがあるだろう」とも言われていたという。これらのことと、自分が紀州出身であることから、改行は自身が吉宗の御落胤であると結論付けたのではないだろうか。もちろん、本人が心から信じていたのかどうかはわからないし、ただ自分の素性が高貴なものであるらしいと、それとなく周りに話したものが広がり、騒ぎが大きくなっただけかもしれない。
捕縛された天一坊改行
改行は吉宗の御落胤と称し、彼が幕府で重鎮となったときのおこぼれを期待した商人や町人からの献金を受けたり、仕官を願う浪人から金品を受け取ったりしていた。その行動を不審に思った本多儀左衛門という浪人が関東郡代の伊奈半左衛門に通報する。伊奈は、万一御落胤が真実だとすると大変なことなので、慎重に内偵を行う。その結果、天一坊改行が吉宗の御落胤だというのは嘘であると判断された。ちなみに、ここまでの吟味に大岡忠相は一切関与していない。
御落胤と詐称して世間を騒がした罪で、改行は死罪の判決を受ける。享保14年(1729)4月21日。天一坊改行は、鈴ヶ森刑場で斬首された。享年31歳。
真偽のほどは?
天一坊が本当に吉宗の子だったのか、全くの他人だったのか。DNA鑑定などが存在しない時代、真実はわからないが、もしも本当に御落胤だったとしても、天一坊は処刑されていたかもしれない。すでに江戸幕府の安定期に入っていた吉宗時代、突然現れた将軍の後継ぎなど、争いの種でしかない。これを認めてしまえば、いくらでも偽物が現われる可能性も大きい。幕政を揺るがしかねない面倒事はさっさと消してしまうに限るのである。
「天一坊、吉宗御落胤は若い命を幕府に奪われた」なんて、裏読みしすぎか…。
あとがき
今回、面白そうな江戸時代の事件という程度で調べてみるうち、天一坊はただ父という存在にあこがれただけではないかと思った。天一坊の本当の心はわからない。しかし、紀州で生まれ、母や伯父から高貴な血が流れているとほのめかされた彼が、天下の将軍・吉宗が父ならと夢を見たとしても、不思議ではない。
将来に不安を持った若者がふと見た夢、それが御落胤だったのではないだろうか。そんな彼に近づいたコバンザメのような大人たち。天一坊は、欲にまみれた人間たちの神輿に乗せられ、そして殺された…。
天一坊事件は、創作意欲をくすぐる事件のようだ。
【主な参考文献】
- 歴史の謎研究会『仮説の日本史』(青春出版社、2022年)
- 邦光史郎『日本史夜話』(廣済堂出版、1991年)
- 大石学監修『知れば知るほど面白い 徳川将軍十五代』(実業之日本社、2012年)
- 河合敦『おもしろくてためになる日本史の雑学事典』(日本実業出版社、2002年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
日本史全般に興味がありますが、40数年前に新選組を知ってからは、特に幕末好きです。毎年の大河ドラマを楽しみに、さまざまな本を読みつつ、日本史の知識をアップデートしています。







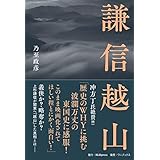



コメント欄