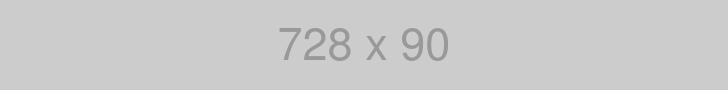
江戸時代の島流し 流罪決定~出航前~出航~航海…流人たちが江戸を離れるとき
- 2024/01/23

江戸時代、「伊豆七島」と言えば「流人」と返ってくるほど、この島々は流人の島として認知されていました。島帰りの言葉もありますが、ほとんどの流人は戻ってくることはありません。そんな流人たちはどのようにして江戸を離れて行ったのでしょうか?
年3回の流人船
江戸時代中期まで、幕府は流罪人が発生すると、七島支配奉行(初期は下田奉行のちには浦賀奉行が兼務)に伝え、支配奉行から船を出して流刑地の島へ知らせます。知らせを受けた島は、自前で漁船か廻船の迎えの島船を出し、流人と警護の役人を乗せて島へ連れ帰ります。その後、また島船で役人を江戸へ送り返すという何とも煩雑な方法を取っていました。厄介者の流人を背負いこむのに、費用も労力も負担せねばならないため、これでは島の方に不満が溜まっていきます。
寛政8年(1796)、幕府は江戸鉄砲洲十軒町に “伊豆七島物産売捌所” いわゆる島会所を開きます。ここで島の物産大島の椿油や八丈島の黄八丈紬などを売り、その金で島での生活必需品を買い整えて島へ運ぶシステムで、会所所属の交易船も用意されました。このシステムが出来てからは、流罪人を運ぶのにも最初の奉行所からの通達にも交易船が利用され、流人運搬の業務は格段に簡便になります。
送られる流人たちですが、罪を犯した者たちに奉行が吟味した結果、遠島が申し渡されます。奉行は直ちに月番老中に上申、老中から島支配奉行に通知が届き、島奉行はそれぞれの島に通達します。この後、流人たちは年に春・夏・秋の3回就航する七島巡回の交易船の船出を待ってそれに便乗、島へ送られることになります。
年に3回ですから採決の時期によっては、流人は4ヵ月ほども小伝馬町の牢で待たねばなりませんでした。もっとも牢内ではあっても、ともかくお江戸の地にまだ居られると思った流人もいたようです。
出航前日に告げられる「島割り」
流人がどの島に流されるのかを決めるのを「島割り」 と言いました。これが本人に知らされるのは出航の前日です。しかし家族には数日前に奉行所から通知があり、通知を受けた家族は流人が島へ持って行ける品々を携えて駆けつけます。米や麦は結構な量を、銭なら20貫文金は20両まで持って行くことができました。もっとも身分のある武士や裕福な町人ならいざ知らず、制限いっぱいまで持って行ける流人などはめったにいません。住所も定まらぬ無宿者や水呑百姓の多かった流人たちは大抵、着の身着のままの無一文で流されていきます。お上のお慈悲としていくらかの銭が支給され、与えられた布団は持って行けましたが、刃物や書物・火道具の類は許可されませんでした。
出航前日になると、罪人たちは手錠・腰縄ではありますが、牢舎の前に引き出され、明日の出立と行先を告げられます。筵の上に座って髪を整えてもらい、医者による診察も受け、新しい着物とお手当銭、身寄りからの届けものも与えられます。
その晩は最後の夜だからと食事にも小さいながら尾頭付きの魚が膳に上り、本人が希望すればお手当銭の中から好きな食べ物や酒を買ってもらえたようです。
出航当日
定めの時刻になると、流人たちは牢舎の前に引き出され、元の身分が武士や僧侶だった者は駕籠に、それ以外の庶民は後ろ手に縛り上げられ、所持金は持ち主の名前の木札を付けてまとめられます。準備が整うと、南町・北町両奉行所の出役与力その他一同が立ち合い、鍵役が出牢証文と照らし合わせて流人を改め出役与力へ引き渡します。牢屋裏門から出された流人は、御船手番所の船手頭(ふなてがしら)の指図で船に乗せます。船着き場は永代橋や万年橋・霊岸島などその時によって変わりました。河岸にはすでに交易の荷物を積み込んだ交易船が横付けされ、流人の乗船を待っています。前後を水手同心に警護され、数珠つなぎで一列になって川岸から掛けられた踏み板を渡って乗り込みます。江戸の土地を一歩離れれば行く先は二度と戻れぬ荒海の果て、鬼の住むという流人島です。
最後の別れ
岸を離れるまでは絶対に人を近づけなかった流人船ですが、艫綱(船を陸につなぎとめる綱)を解き、川面に漕ぎ出すと、どこからともなく数隻の小舟が近づいてきます。流人船の大きな船腹に追い縋り、棹を操る船頭たちが慣れた口調で次々に呼びかけます。「お願いでございます、お願いでございます。何某の縁者でございます、お慈悲を以って一目だけでも最後の別れを」
陸では許されなかった最後の対面を願い出るのを、役人たちは見て見ぬふりをしました。佃島の近くにはこの最後の別れを願う縁者たちを船に乗せる船頭たちがいました。この船頭たちは日ごろから役人に心付けを渡しておいたそうです。
最後の別れとはいっても、互いに言葉も交わせず、顔を見つめあうだけでした。
島への航海
流人船の交易船は500石積み程度で、船頭・水夫8人で操ります。流人の護送役として、いずれも御船手番所の船手同心の主任1人と助手3人も乗り込みます。航海中流人たちは木格子で隔てられた船底の船牢に押し込められます。櫓の前方に長さ三間・横幅六尺・高さ四尺の船牢があり、中に三尺四方の便所が切ってあります。高さ四尺と言えば立ち上がることも出来ません。船牢は1つしかないので、どの島へ送る流人もまとめて収容します。またお目見え以上の流人や女の流人は、船内に別の囲いを設けて収容しました。
さすがに流人たちの綱は解かれましたが、海の関所・浦賀番所を通過するまでは牢から一歩も出られません。やがて浦賀沖に差し掛かると番所から役人が船に乗ってやって来ます。流人を牢から引き出し甲板に座らせて送り状と見比べながら一人一人首実検です。
「武州国分寺村百姓、何某。罪状○○により三宅島へ遠島、当人に相違ないか」
「へえ、違いございませぬ」
こんな問答も終わり、浦賀の番所も無事超えられました。船内の警護も緩やかになり、時には流人たちも甲板に出て陽の光を浴び辺りを歩き回ったりできます。
おわりに
この後は順調にいけば三宅島までは4日、黒潮本流を乗り切る八丈島へも5日の航海ですが外海は荒れることも多く、そうなれば5日10日と途中の港に逃げ込み風待ちせねばなりません。それでも難破する船もありますが、その記録はほとんど残っていません。【主な参考文献】
- 大隈三好『遠島』雄山閣/2003年
- 水野大樹『「拷問」「処刑」の日本史』カンゼン/2015年
- 渡邊大門『流罪の日本史』筑摩書房/2017年
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
Webライターの端っこに連なる者です。最初に興味を持ったのは書く事で、その対象が歴史でした。自然現象や動植物にも心惹かれますが、何と言っても人間の営みが一番興味深く思われます。







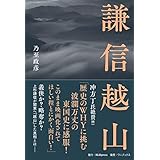







コメント欄