関ヶ原脱出劇「島津の退き口」 島津義弘はどうやって薩摩へ辿り着いたのか?
- 2023/11/14

「主を逃がすため」そう覚悟して次々に倒れていく家臣たち。彼らの決死の働きによってようやく狭い関ヶ原から脱出できた島津義弘。しかし、戻るべき故国・薩摩国ははるか彼方です。義弘はどうやって薩摩にたどり着いたのでしょうか?
味方も少なく関ヶ原を脱出する島津義弘
天下の決戦・関ケ原合戦(1600)もわずか半日の戦いで東軍の勝利に終わりました。西軍に付いた島津義弘の周囲には、関ヶ原を脱出した時、50ほどの家臣しか残っていませんでした。もともと国元からの出兵を兄・義久に止められ、義弘が決戦に率いたのはわずか1500、その兵たちも討ち死にしたりはぐれたりと減るばかりです。脱出後の義弘は西軍が本拠地とした大垣城に入って味方と合流するつもりでした。しかし南宮山のあたりから望んだ大垣城は、すでに火の手が上がっているのが見えました。城の守備を任された相良頼房や秋月種長らが寝返り、味方の首を取って東軍に許しを請うていたのです。
大垣城をあきらめた義弘隊は伊勢を目指しました。途中、麓を通る栗原山には、西軍の長宗我部盛親、長束正家、安国寺恵瓊が陣を張っています。義弘はその陣へ使いを送ります。後日、自分が戦いもせずに戦場を逃げ出したのではないことを証明してもらうためです。
それぞれから「関ケ原でのお手柄は見事なものでした」とか「申し分ないお働きでした」との返事を得、正家からは道案内の者1騎が送られて来ます。その者を先に立てて正家の城・水口岡山城を目指しますが、家康が京都に向かうとの報を受けて、鉢合わせを避けるために伊勢への道を取ります。
水口から土山、信楽を抜けて和泉の国へ
なおも先を急いで大道に来かかると、東軍の軍勢が進軍中です。「ここに至っては仕方も無い。切り崩して押し通れ!」
義弘の号令一下、大軍を横切る島津勢ですが、相手も油断していたのか、まさか島津勢とは思わなかったのか、一兵も損なうことなく渡り切ります。その後、伊勢の関(三重県亀山市)に着いたのが暮れ六つのころ(午後6時ごろ)。ここで家康がすでに京都に入ったとの知らせを受けます。京都経由で薩摩に戻るのを断念した義弘は、伊賀から信楽をぬけて和泉国・堺への道を目指します。
島津家と取引のある堺の商人を頼ろうとしたのですが、すでに16日の夜になっていて道もわかりません。近在の者を捕まえて道案内に立たせ、ついでに食料も奪うように手に入れます。17日の朝、案内人に「もはや和泉国です。お暇を下され」と言われ、「褒美を取らせたいが金もない」そう言いながらも銀子1枚を与えます。銀子1枚は43匁ですから35万円ほど、怖い思いもしたでしょうが案内人は十分な報酬を得ました。
やっとの思いで和泉国へ
大坂と京都の分かれ道で石田三成から付けられた入江忠兵衛らに暇を与えます。摂津住吉の法明寺に着いたのは関ケ原合戦から4日後の事でした。もともと島津家と大坂住吉とは縁がありました。島津家の初代当主・島津忠久(1179~1227)は源頼朝の落とし胤と言われ、身ごもった側室が嫉妬深い北条政子の許を逃れる途中、雨の住吉大社で狐火に守られながら忠久を生んだと伝わります。
寺は門を閉じて一行を匿いますが、ここに来て義弘が弱気な事を言いだします。
「ここまで来たものの国へ帰る手立ても無い。儂は腹を切るからお前たちはなんとしてでも国へ帰り、龍伯様(義久)にこのことを伝えてくれ」
家臣たちは引き止めたり差し違える相手を探したりでうろうろしますが、それを見て義久またも言い出します。
「こうなれば行く末を見届けよう、おまえたちもそれまでは自害をするな」
多分家臣たちを引き締めにかかったのでしょうね。
その夜になり、堺の商人・塩屋孫右衛門が乗り物を用意して法明寺に迎えに来ます。義久は使いを出して大阪の屋敷にいる妻や息子忠恒の妻の安否を探らせ、自身は堺へ向かいます。
孫右衛門の土蔵に匿われた一行に湯漬けと香の物を出した孫右衛門、3歳になる自分の孫を義久の膝に置き
「秘蔵の孫を質に出しますのでお気を安らかに」
と言ったとか。この時、孫右衛門の店表にも居宅にも東軍の『家探し奉行』が投宿しており、日々西軍の落ち武者を切り捨てている状況でした。東軍と西軍がひとつ家の内で鼻突き合せて潜んでいました。
脱出してきた妻との再会
孫右衛門の家に逗留するうちに大坂から使いに出したものが戻って来て「亀寿殿(忠恒の妻)も宰相殿(義弘の妻)もご無事です」と報告します。義弘が西軍に味方したので、大坂城に呼び出されることもなく、島津屋敷に留まって居られました。そこで再度大阪へ人を遣り、大坂城へは「義弘は関ケ原にて秀頼様への御奉公のため討ち死に、人質は国許へ戻れるようお計らいを」と申し入れさせます。もちろんウソですが、大坂城には毛利輝元が陣取っており、まだ家康の手は入っていません。城は夫を失ったはずの妻たちを不憫に思い、帰国を許します。
21日になって孫右衛門の屋敷の浦へ船をつなぐ者があります。見ると義弘の御座船の船頭東太郎左衛門、双方相手を認めて大喜びしこれでやっと薩摩へ帰る手立てが付きました。
22日の早朝七つ時分(午前5時ごろ)御座船にのって大坂河口までやって来た義弘は約束の刻限を待ちます。正午になり、家老の平田増宗が船でやって来ると、2人の奥方が大坂から船に乗り、無事に番所を過ぎたことを告げます。
大坂屋敷に居た女子供と、増宗が残しておけば危ないと判断した西軍に付いた日向財部城主・秋月種長の妻もみな乗船していました。兵庫西宮の沖で両船は行き会い、妻たちは義弘の船に移り、無事の再会を喜び合います。
亀寿は島津家系図を持ち出しており、宰相は文禄の役(1592~93)の恩賞として秀吉より賜った名物茶入れ “平野肩衝(かたつき)” を懐に忍ばせていました。武将の妻らしい2人の落ち着いた振る舞いは義弘を大いに喜ばせます。
立花宗茂との再会
義弘と同じく西軍として関ケ原に参戦した九州の大名・立花宗茂、こちらも50余りの船に分乗し、故国の柳川を目指します。同じルートを辿ると聞いた2人は連絡を取り合い、安芸の日向泊まりに船をつないで再会、抱き合って涙を流して喜びました。義弘一行の船は豊後灘で東軍の黒田如水の番船に囲まれ海戦、伊集院左京・大重次郎兵衛らを失いますが、なんとか振り切って29日に日向細島へ着船します。その後、冨隅城に兄の島津義久を訪ね、
義久:「大敵の囲みを破っての無事生還、人質の女子供も取り戻すなど並の武将が出来る事ではない」
との言葉を掛けられます。「兄者がもっと兵を寄こしてくれれば良かったものを」義弘心の内で呟いたことでしょうね。
おわりに
義弘は九州の雄島津家が1500の寡兵で関ケ原に望んだことを口惜しく思っていました。引き籠った陣中で「我に5000の兵ありせば、我に5000の兵ありせば」と繰り返していたと言います。【主な参考文献】
- 山本博文「「関ケ原」の決算書」新潮社/2020年
- 渡邊大門/編「関ケ原合戦人名事典」東京堂出版/2021年
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
Webライターの端っこに連なる者です。最初に興味を持ったのは書く事で、その対象が歴史でした。自然現象や動植物にも心惹かれますが、何と言っても人間の営みが一番興味深く思われます。

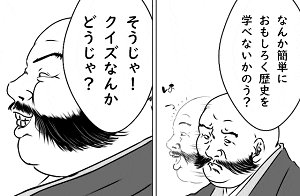
コメント欄