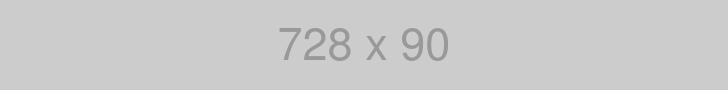
陸軍大臣「阿南惟幾」は、日本を救うためにわが身を犠牲にしてくれた
- 2023/06/30

昭和42年(1967)に公開された日本映画『日本のいちばん長い日』は半藤一利氏のノンフィクション作品を映画化した物ですが、陸軍大臣である阿南惟幾(あなみ これちか)大将の役を三船敏郎さんが演じています。
三船敏郎さんといえば、世界的な評価を得た黒澤明監督が最も重用した俳優であり、「強く、逞しく、芯の強い男」を体現していた方です。当然ながら、そんな三船敏郎さんを端役にあてるはずなどありません。この映画を監督した岡本喜八監督も「いかに阿南大将役が大事であるか」を理解したうえでのキャスティングでした。それくらいに太平洋戦争における日本の敗戦受け入れの過程で、阿南陸軍大臣の果たした役割は重要だったのです。
敗戦までのシナリオを描いたのは鈴木貫太郎総理大臣でした。しかし、そのシナリオを実行するには阿南陸軍大臣の存在が必要不可欠でした。『日本のいちばん長い日』は昭和20年(1945)8月14日に起きた「宮城占拠事件」を中心に描かれていますが、現実の敗戦受け入れ処理は、同年の4月7日に鈴木貫太郎内閣が発足する直前から既に始まっており、運命の8月15日を迎えるまで、およそ4か月半に渡り「長い長い一日」が続いたのです。
その「長い長い4か月半」に阿南陸軍大臣が、どのようにして鈴木総理を助けたのかを述べてみたいと思います。
三船敏郎さんといえば、世界的な評価を得た黒澤明監督が最も重用した俳優であり、「強く、逞しく、芯の強い男」を体現していた方です。当然ながら、そんな三船敏郎さんを端役にあてるはずなどありません。この映画を監督した岡本喜八監督も「いかに阿南大将役が大事であるか」を理解したうえでのキャスティングでした。それくらいに太平洋戦争における日本の敗戦受け入れの過程で、阿南陸軍大臣の果たした役割は重要だったのです。
敗戦までのシナリオを描いたのは鈴木貫太郎総理大臣でした。しかし、そのシナリオを実行するには阿南陸軍大臣の存在が必要不可欠でした。『日本のいちばん長い日』は昭和20年(1945)8月14日に起きた「宮城占拠事件」を中心に描かれていますが、現実の敗戦受け入れ処理は、同年の4月7日に鈴木貫太郎内閣が発足する直前から既に始まっており、運命の8月15日を迎えるまで、およそ4か月半に渡り「長い長い一日」が続いたのです。
その「長い長い4か月半」に阿南陸軍大臣が、どのようにして鈴木総理を助けたのかを述べてみたいと思います。
【目次】
鈴木貫太郎侍従長に総理大臣が下命された事情
鈴木貫太郎氏は元々は海軍の軍人でしたが昭和天皇、皇后の「ご指名」で侍従長になった、という変わった経歴の持ち主でした。そして戦局悪化の責任を取って小磯国昭内閣が総辞職すると、昭和天皇から次の総理大臣に指名されてしまったのです。こういう書き方をする理由は、鈴木貫太郎侍従長は国会議員でも軍人でもなく既に77歳と言う年齢で、しかも政治経験ゼロという人物であったからです。つまり、極めて異例な「ご指名」であり、鈴木侍従長は重ねて固辞しますが、昭和天皇自ら
「鈴木の心境はよくわかる。しかし、この重大なときにあたって、もうほかに人はいない。頼むから、どうか曲げて承知してもらいたい」
とまで言われ、本人も受ける決心をしたのです。

昭和天皇がそうまでして鈴木侍従長を総理大臣に指名した理由は、ひとえに「もう戦争を終わらせたい」という御希望を叶えるためでした。
こう書くと、現代に生きる皆さんは、「当時の天皇陛下といえば、現人神であり、絶対権力の持ち主だったのだから ”もう戦争は終わりにする” と言うだけで済んだのではないか? 」と思われるかもしれません。しかし、現実はそうではなかったのです。既に陸軍を中心とする暴走は憲法上、統帥権を持つ天皇陛下でも止められない状況になっていたからです。
その一例として「宮城選挙事件」の主謀者の一人である畑中少佐の言葉を挙げてみましょう。
天皇には国民を救うためとはいえ、"わが身はどうなっても"などという自由はないはず。天皇の神聖は有史以来のものであり、天皇自身もその点を深く考慮されねばならない
一見、筋の通った意見とも取れますがよく考えると、あまりにも身勝手すぎる意見であり、これは陸軍の過激派に共通したものでした。いわば「天皇陛下はこうあるべきだ。だから天皇陛下のために我々は現状を正さなければいけない」という論法です。これでは天皇陛下が自ら意見を述べても反論されてしまいます。実際に「天皇陛下の御為に」と唱えながら彼らは過激な行動に出て二・二六事件を起こし、ひいては太平洋戦争を起こしてしまったのです。
ここで問題になるのが「統帥権」という問題です。統帥権とは「指揮・統率する権利」を言いますが、当時の大日本帝国憲法では陸軍、海軍の統帥権(最終的な命令を出す権利)は天皇陛下にあると規定されていました。ですので軍のトップである陸軍大臣、海軍大臣は「軍のトップとして内閣に参加している」だけなので、たとえ総理大臣といえども、陸軍や海軍に命令を出すことはできません。それが陸軍の暴走を許すことにつながりました。
身勝手な意見を決して変えようとはせず、「軍人は勝利か死か、のどちらかである」と教育されてきた陸軍の過激派メンバーらは、内閣を軽視して自分達の意見をゴリ押しする形で物事を進めてきました。その結果、軍人・民間人に大量の死傷者が出てしまい、今や日本という国の存続も危ぶまれる事態にまで至ることになったのです。
このため、昭和天皇にも戦争を簡単に終わらせることは不可能でした。何を言っても陸軍は言うことを聞かないのですから。つまり、昭和天皇は鈴木貫太郎侍従長に「最後の望み」を託したということです。
問題は陸軍大臣を誰にするか?
総理大臣を引き受けた鈴木貫太郎氏は、組閣する前に、まず市ヶ谷にある陸軍省へ行きました。戦争を終わらせるためには自分の意図を阿吽(あうん)の呼吸で理解し、実行してくれる人に陸軍大臣になってもらう必要があったからです。そうした人が唯一、阿南惟幾大将でした。
阿南大将は4年間、天皇陛下の侍従武官として皇室内で鈴木侍従長と一緒に、天皇陛下に直接お仕えした経験があり、鈴木侍従長は阿南大将の人柄を良く知っていました。そして阿南大将なら何も言わずとも、自分の意図を理解し実行してくれるであろうことを確信していました。
阿南大将は軍人としての功績は多くはなく、また知性的に優れているとか、策略に長けているという人物ではありませんでした。人に気を使う性格で優しくて視野も広い人でしたが、何よりも「並外れて優れた性格の良さ」を持つ人でもありました。もちろん軍人ですので厳しさも持ち合わせていたのですが、鈴木侍従長は阿南大将が昭和天皇に対し、計り知れない深い尊敬の念を持っていることを知っていたのです。
また、昭和天皇も阿南大将を「あなん」と呼んで親しくされており、厚い信頼を抱いていました。その点は鈴木侍従長も同じでしたので、お互いに「阿吽の呼吸」で言葉を交わさずとも意図するところを理解してくれる唯一の人物だったのです。
陸軍省で応対した杉山元帥陸軍大臣に、鈴木貫太郎氏は「次の陸軍大臣には阿南大将をお願いしたい」という要望を出しました。すると、杉山元帥は他の幹部及び阿南大将自身にも意向を確認し「条件付き」で阿南大将の入閣を了承する、と伝えてきました。
その条件とは以下の3つです。
- あくまで戦争を完遂すること
- 陸海軍を一体化すること
- 本土決戦必勝のため、陸軍が企図する諸政策を具体的に躊躇なく実行すること
本来なら「戦争を終わらせる」ことが目的で総理大臣になるのですから、とても飲める条件ではありません。しかし鈴木貫太郎氏は、いとも簡単にあっさりと「了解しました」と言って受諾したのです。
ただ、この条件を守るつもりなど全くありません。目的は「天皇陛下のご希望を叶えること」であり、その結果、自分がどうなろうと構わないと覚悟していたから出た言葉でした。
鈴木侍従長に会った阿南大将は、いきなり「書記官長は誰ですか?」と質問してきました。鈴木氏が迫水久常氏であることを告げると、阿南大臣は「分かりました。やりましょう」と言ってくれたのです。これぞまさに「阿吽の呼吸」でした。
迫水久常氏は終戦にあたり、色々な場面で機転を利かせた処置を行い、鈴木総理を助けた人物ですが、阿南大将と面識はありませんでした。しかし「和平論者」ということで有名であり、憲兵隊にマークされていた人物でもあったのです。
こうして阿南大将が陸軍大臣に就任することになりました。

必死の演技
昭和20年(1945)4月7日に鈴木内閣が発足。まずは陸軍の過激派メンバーに「終戦を目的とした内閣」であることを悟られないことが重要でした。もしそれを知られたら過激派メンバーがクーデターを起こすことは火を見るより明らかだったからです。このため、鈴木総理は国民に向かって「戦争遂行」を呼びかけ、阿南陸相は閣議の席でも強硬論を唱え続けました。過激派のメンバーは鈴木総理が異例の経緯で総理になったことに不信感を抱いており、「もしかして終戦を企んでいるのではないか」と見張っていました。さらには、どういう経路かは分かりませんが、閣議の内容が過激派メンバーに筒抜けとなっており、鈴木総理、阿南陸相は動向を探られてもいました。いつ、いかなる場合でも「終戦目的」という意図を悟られないよう、二人は気を抜かずに必死の演技を続けたのです。
日々戦況が悪化していく中で、他の閣僚からは「もう戦争は無理では」という意見が出ると、阿南陸相は猛反対し、まだ戦うべきであることを強硬に主張しました。一方、鈴木総理は閣議でも「聞いているのか、いないのか良く分からない」ような態度に終始して、腹のうちを読ませないよう努めていました。しかし外向けには戦争継続を主張し必死の演技を続けました。
閣議が終わって阿南陸相が軍省に戻ると、過激派将校達が閣議の様子を聞きに集まってきます。そして「陸軍として主張すべきことを主張してきた」と言って皆を満足させていたのです。
閣議のメンバーの中には二人の真意を察する事なく、「あくまで強硬論」を貫く阿南陸相に食ってかかるメンバーも出ました。海軍大臣の米内光正大将は和平派で「もう戦争は止めにした方が良い」と公然と口にしていました。海軍には陸軍のような過激派は少なかったのです。
米内海相は鈴木総理の政治力の弱さに危惧を抱いており、議会での紛争に嫌気が差して辞表を提出しようかと考え始めますが、それを察した阿南陸相から手紙が届きます。
それには「辞職は思いとどまって頂きたい。後で私の意のある所をお伝えしたい」と書いてありました。
もし米内海相が辞任した場合は内閣不一致ということになり、鈴木内閣は総辞職となって全てがダメになってしまいます。阿南陸相の手紙を読んだ米内海相は辞職を思いとどまります。
当時、東郷外務大臣は連合国側ではないソ連に対し、和平の仲介役を依頼する打診を行っており、その線に一縷の望みを抱いていました。しかし阿南陸相は「ソ連は信用できない。その線はダメだろう」と悲観的な観測をしていたそうです。
とにかく時が満ちるのを待つ、それまでは必死の演技をするしかなかったのです。
ポツダム宣言の発令と原爆の投下
昭和20年(1945)7月26日、イギリス、 アメリカ合衆国、中華民国の政府首脳の連名において日本に降伏勧告が発せられました。いわゆるポツダム宣言です。最初、この宣言は外務省に入り、宣言内容を精査した東郷外務大臣を含む外務官僚は「今はソ連に仲介を依頼しているので、その回答が来るまで様子を見たほうが良い」と言う結論に達し、閣議でもそのように報告しました。その結果、鈴木総理は記者会見で
「あの共同声明はカイロ会談の焼き直しであると考えている。政府としてはなんら重大な価値があるとは考えない。ただ 黙殺するだけである。われわれは戦争完遂に邁進するのみである」
と述べてしまいました。
新聞は「笑止!米英共同宣言、自惚れを撃砕せん、聖戦を飽く まで完遂」「政府は黙殺」と書き立て、海外のマスコミは「日本はポツダム宣言受け入れを拒否した」と捉えたのです。
実はポツダム宣言文には最後に
「われらは右条件より離脱することなかるべし」
と書かれており、事実上の「最後通牒」だったのですが、誰もそれに気が付きませんでした。
日本は受け入れを拒否した、と判断した連合国側は8月6日に広島、8月9日に長崎に原爆を投下し、圧倒的な力の差を見せつけ、さらに降伏を迫るという手段に出ました。
米国のトルーマン大統領は
「われわれは二十億ドルを投じて歴史的な賭けをおこない、そして勝ったのである……六日、広島に投下した爆弾は戦争に革命的な変化をあたえる原子爆弾であり、日本が降伏に応じないかぎり、さらにほかの都市にも投下する」
という声明を伝えてきました。広島、長崎の惨状は目を覆わんばかりのものでした。
8月10日の午前に最高戦争指導者会議が開催されましたが、席上、阿南陸相は敵軍捕虜から得た情報として、「米軍の次の攻撃目標は東京である。米国は同爆弾を100個余りを保有し、今なお一か月に3個のペースで製造を行っているとのことである」という報告を行います。
実はこれは全くのデタラメなのですが、この阿南陸相の報告は内閣のメンバーを凍り付かせるに十分でした。会議は昼に一旦、休憩となりますが、その日の午後、鈴木総理と東郷外相は宮中を訪れ、最高戦争指導者会議を御前会議(天皇陛下も出席される会議)として開催したい旨を告げ、了承を取ってきます。そして、深夜12時に宮中にて御前会議としての最高戦争指導者会議が開催されることになりました。議題はポツダム宣言を受諾するか否やです。
これが鈴木総理が描いていたシナリオでした。つまり、昭和天皇ご自身の口から「降伏し終戦とする」という言質を頂くことだったのです。天皇陛下のご意見に直接的に反対することは誰にも出来ません。二・二六事件の時も、いわゆる「ご聖断」で兵を起こした部隊は「反乱軍である」として処罰されたのです。
「ご聖断で和平への道を切り開く」という単純な手段でしたが、最も効果的な方法でもありました。「ご聖断(天皇の決断)」であれば、陸軍でクーデターが起きてもすぐに反乱軍と決めつけることができるので対処しやすく、クーデターを起こそうとする側も躊躇せざるを得ないだろう、という見込みもあったのです。
第1回御前会議
8月10日の深夜12時近く、宮中にある防空壕で最高戦争指導者会議が始まりました。しかし結論はまとまりませんでした。受諾と言う点では一致していたのですが、無条件ではなく何等かの条件をつけるべきだ、ということになり、どういう条件をつけるかで紛糾してしまったのです。
…というよりも阿南陸相が意図的に「最低でも4つの条件をつけなければ受諾すべきでない」と述べ、他の中道的な意見に対して強硬な反対論を唱えていたのです。
天皇陛下がご意見を言う前に”全会一致”で結論が出てしまっては困るのです。ここはなんとしても紛糾させ、「陛下のご判断を仰がなければならない」状況にしなければなりませんでした。そのため、阿南陸相は熱弁を振るい続けます。そして午前2時に近くなると、鈴木総理は立ちあがり、
「意見の相違がある以上、甚だ畏れ多いことながら私が陛下の思し召しをお伺いし、聖慮をもって本会議の結論と致したいと思います」
と述べて、天皇陛下の前に進み出ました。
昭和天皇は「ならば私の意見を言おう」と、東郷外相の案に賛成である旨を述べられました。2人の努力が実を結んだ瞬間でした。東郷外相の降伏案は「皇室の存続のみを希望し、後は条件を付けない」という最低条件の案だったのです。
会議は午前2時半に終了しました。会議が終わり、一同が退出するときに、吉積軍務局長が「約束が違うではありませんか!」と鈴木総理に詰め寄りました。
御前会議を開く際には総理大臣と参謀総長、軍令部総長の事前了解が必要であり、それは迫水秘書官が取りつけていたのですが、その際に「終戦の話ではない」ということで了解を取っていたのですが、実際には終戦の決定であったからです。
すると、阿南陸相が割って入り、
「吉積!もうよいではないか!」
と鋭くたしなめ、さらに続けました。
「私は陛下に対し徹底的に陛下のご意思に反する意見を申し上げた。これは万死に値する。またポツダム宣言受諾となれば、この敗戦の責任は陸軍を代表して私が腹を切る。お前らは軽挙妄動するな!」
米軍の回答と危険の再燃
第1回御前会議の結果は外務省から米国政府に通達されましたが、それに対して米国から返事が届きました。英文ですので和訳をお見せしましょう。(1)降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為、必要と認められる措置を指揮する連合国軍最高司令官の制限下に置かれるものとする。
(2)最終的な日本国の政府の形態はポツダム宣言に従い、日本国国民の自由に表明される意思により決定されるものとする。
これは主に外務省の翻訳に従っていますが、(1)の「制限下に置かれる」の原文は subject to という表記で意味としては「隷属する」という意味にも取れました。「制限下に置かれる」というのは軍部を刺激しないよう外務省が苦心して編み出した訳文であったのです。
しかし陸軍は陸軍で独自の翻訳をし「隷属するとは何事だ!」ということになってしまいます。過激派将校は大臣室にやってきて「宣言受諾は拒否すべきだ!」と騒ぎ立てる事態となりました。
懸念していた陸軍過激派のクーデーターが今にも勃発しそうでした。クーデーターを懸念した阿南陸相は閣議で「この回答は受け入れられない」旨を訴えます。この時、阿南陸相には首都クーデターとともに満州国の関東軍を始めとする外地部隊の反乱が脳裏をよこぎっていた、とも言われます。
”もし、このままの状態で終止符を打つと、どこで大規模な反乱が起きるか分からない。もしそれが起こったら占領米軍と砲火を交えることになりかねない。そうなったら、米軍は徹底的に反乱軍を鎮圧するだろう。そして、その分だけ日本は米国により多く苦しめられることになるだろう……”
この閣議の最中に阿南陸相は迫水秘書官に合図を送り、別室に移ります。何事かと思った迫水秘書官の前で阿南陸相はクーデーターを画策している一人である荒尾軍事課長に電話をかけ、「今、閣議中であるが、閣僚の意見はみな、陸軍の意見に賛成であるから心配しないように」と話しはじめたのです。
もちろん、全くの虚偽です。そして「もし疑うのであれば、今、迫水秘書官が横にいるから彼から説明させても良い」と言うのです。陸軍が暴挙に走らないようにするための手段でした。
迫水秘書官は驚愕しましたが、阿南陸相の真意をはじめて知る機会でもありました。そんな阿南陸相の懸念を感じとった鈴木総理は再度、御前会議による最高戦争指導者会議を行うことを決断します。

第2回御前会議
「陛下のお召」という形で第2回目の御前会議による最高戦争指導者会議が8月14日に宮中の防空壕で行われました。しかし特に新しい意見はなく、阿南陸相が「回答について米国に照会してみるべきかと存じます」と言い、続いて梅津参謀長も同様の意見を述べました。そして最後に豊田軍令部総長が「このままで和平を迎えるのは反対で御座います」と述べました。そして鈴木総理が「反対の意見はこれだけで御座います」と申し上げると、昭和天皇は自ら口火を切りました。
「ほかに意見が無いようだから私の意見を述べよう。みなの者は私の意見に賛成してほしい」
「3人が反対する気持ちは良く分かるし、その趣旨も分からないではないが、私の考えは、この前、申したことに変わりは無い」
「自分の身はどうなってもよいから国民の命を助けたい。必要であれば私がマイクの前に立っても良い」
「3人が反対する気持ちは良く分かるし、その趣旨も分からないではないが、私の考えは、この前、申したことに変わりは無い」
「自分の身はどうなってもよいから国民の命を助けたい。必要であれば私がマイクの前に立っても良い」
さらに阿南陸相に向かい
「阿南の気持ちもよく分る。苦しかろうが我慢してくれ」
と声をかけられます。その声は少し嗚咽を含んでおり、涙ぐんでおられる様子でもありました。
御前会議後
阿南陸相は2回目の御前会議が終わり、引き続き行われた午前の閣議に出席した後、陸軍省に一旦戻ります。すると、当然のように過激派将校達が阿南陸相に詰め寄りました。「国体護持(天皇の地位不変の意味)の確約が無ければ徹底抗戦ではなかったのか!」
「大臣に決心変更の理由を伺いたい!」
「大臣に決心変更の理由を伺いたい!」
それに対し
「陛下はこの阿南に対し、お前の気持ちは良く分かる。苦しかろうが我慢してくれ、と涙を流して仰せられた。自分としては、もはやこれ以上、反対を申し上げることはできない。御聖断は下ったのである。いまはそれに従うばかりである。不服のものは自分の屍を越えてゆけ!」
と答えました。
次の瞬間、クーデーターの中心的存在であった畑中中佐が号泣し始めたのです。この瞬間に首都における陸軍の大規模なクーデーター計画は、ほぼ消滅したのです。わずかに「宮城事件」と呼ばれる一部の青年将校による玉音放送阻止騒動が起こっただけで済みました。
すべては阿南陸相のおかげでした。しかし、まだ外地部隊の反乱という危険が残っています。それに対し、阿南陸相は「最後の手段」に出ます。
午後の閣議と総辞職
阿南陸相は午後の閣議に出席しましたが、午後の閣議の主な議題は「どうやって終戦を国民に知らせようか」という物でした。新聞発表などの方法では危ないのでは、と危惧していた時に阿南陸相が
「陛下はマイクの前に立っても良いと言っておられた。畏れ多いことだが陛下に放送をお願いしてはどうか」
というアイデアを出しました。
一般国民にとって天皇陛下は御姿を拝することさえ畏れ多く、まして声を聴く機会など全く無かったので、これは効果抜群であるに違いありませんでした。全員賛成となって玉音放送の実施が決定され、早急に用意がはじめられました。つまり玉音放送をする、というアイデアは阿南陸相が考えたことだったのです。
そして閣議が終わり、鈴木内閣は役目を終え、総辞職となりました。総辞職の手続き後に阿南陸相が首相室にいる鈴木総理のところにやってきました。最後の挨拶をするためです。
「終戦についての議が起こりまして以来、自分は陸軍の意志を代表して、これまでいろいろと強硬な意見ばかりを 申し上げましたが、総理に対してご迷惑をおかけしたことと想い、ここに謹んでお詫びを申し上げます。 総理をお助するつもりが、かえって対立をきたして、閣僚としてはなはだ至りませんでした。 自分の真意は一つ、国体を護持せんとするにあったのでありまして、あえて他意あるものではございません。 この点はなにとぞご了解いただくよう」
「阿南さん、あなたの気持ちはわたくしが一番よく知っているつもりです。たいへんでしたね。 長い間本当にありがとうございました。今上陛下はご歴代まれな祭事にご熱心なお方ですから、きっと神明のご加護があると存じます。だから私は日本の前途に対しては決して悲観はしておりません」
「わたくしもそう信じております。これは南方第一戦から届けられた葉巻です。私はたしなみませんので、総理に吸っていただきたく持参しました」
と言い、包みを鈴木の机の端に置くと、敬礼して静かに退出していきました。
「阿南君は暇乞い(いとまごい)に来たんだね」
と鈴木総理は迫水秘書官につぶやきます。
その夜、阿南大将は陸相官邸で切腹し自決しました。これが阿南大臣の「最後の手段」でもありました。翌8月15日に玉音放送とともに阿南陸相自決の報が流れると、徹底抗戦や戦争継続の意見は完全に消え去ってしまいました。

阿南大将は「玉音放送とともに陸相の自決の一報が流されることの効果」を期待していたため、8月14日の自決決行となったのです。その効果のほどを、当時、クーデター計画の中心人物でもあった荒尾軍事課長は、以下のように述べています。
「阿南大将の切腹は陸軍全軍に強いショックを与えた。それは鮮烈なるポツダム宣言受諾の意思表示であった。換言すれば大臣の自刃は天皇の命令を最も忠実に伝える日本的方式であった」
これで陸軍における不穏な動きは完全に払拭されてしまったのです。
陸軍省における最後の訓示で
「過早の玉砕は任務を解決する道ではない。泥を食み、野に伏しても最後まで皇国のために奮闘するように」
と述べ、部下に勝手に自決すること諫め、生きることを命じました。
「腹を切るのは俺一人でいい」
長い長い4か月半でした。
【主な参考文献】
- 角田房子『一死、大罪を謝す』(ちくま文庫、2015年)
- 鈴木貫太郎傳記編纂委員会『鈴木貫太郎傳』(1961年)
- 半藤一利『日本のいちばん長い日(決定版)』(文藝春秋、1995年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
趣味で歴史を調べています。主に江戸時代~現代が中心です。記事はできるだけ信頼のおける資料に沿って調べてから投稿しておりますが、「もう確かめようがない」ことも沢山あり、推測するしかない部分もあります。その辺りは、そう記述するように心がけておりますのでご意見があればお寄せ下さい。












コメント欄