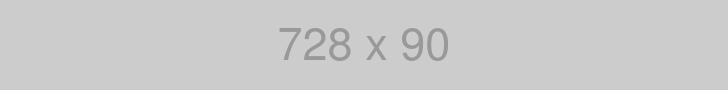
事例からみる戦国初期の男色事情 ~ 細川政元から雄長老まで
- 2022/10/03
乃至 政彦
:歴史家

※内容紹介(戦国ヒストリー編集部より)
男色(なんしょく)とは、男性の同性愛を指す言葉で、いわゆる「BL」のこと。日本において、実は昔からあった「男色」ですが、戦国期の主君と小姓におけるソレは、大半が江戸期に成立した二次史料を基にしているとのことで、俗説にまみれているようです。
実際のところはどうだったのでしょうか? そこで今回は、「戦国武将と男色 ―知られざる "武家衆道" の盛衰史」の著者で知られる歴史家の乃至政彦氏に、戦国初期の男色について、いくつかの事例とともに解説していただきました。
半将軍・細川政元と男色
武士同士(多くは高位の成人男性と、低位の若年男性)の男色は、戦国時代の初期までほとんど事例が見られず、あったとしても武士が僧院の稚児や喝食に手出しするというレベルであった。したがって主君が小姓に色気を求めるということもまだほとんどなかった。ところが15世紀後半から幕府の重臣クラスの間で流行の兆しが見られてくる。半将軍と呼ばれ、幕府内に大変な権勢を振るった管領・細川政元(1466〜1507)はその嚆矢といえるだろう。

政元が養子として手許に置いた澄之の実父・九条政基が下向先で書き記した日記があり(『政基公旅引付』)、文亀4年(1504)11月11日条に摂津守護代・薬師寺元一が政元との紛争に敗れ、自害する時に詠んだ辞世が記されている。
地獄にハ よき我か主のあるやとて 今日おもひたつ旅衣かな
薬師寺元一はかつて政元のもとで働いたことのある部将である。元一は辞世を披露する時に、「政元様は若衆がお好きであった。我が主(わがしゅ)は若衆(わかしゅ)の意味だ」と説明を付け加えた(森田恭二『戦国期歴代細川氏の研究』)。
この辞世から、政元と元一の間に男色が介在していたと想像されている。政元と争って自害する直前「地獄にはいい主人がいるだろうか」と現世への失望をにじませているのをどう評価するかだが、普通に考えれば、元一自らの視点としてそういう感傷を描き、同時にもと主君の政元視点で、元一と地獄で仲直りしたいという気持ちを想像してこれを重ね合わせたものであろうから、通説の解釈で読み解いていいように思う。いずれにしても、ここに政元の若衆好きが隠れなき事実だったことを確かめられる。
3年後の永正4年(1507)10月に書かれた『九郎澄之物語』も、政元が女性を寄せ付けず、実子を儲けなかったことを特筆している。
政元は終生、女性を好まなかった。男色だけを嗜む武士は史料上にとても希少で、政元の例は珍しいものだったといわざるを得ない。一説には魔法修行のため、女人禁制を守り通していたといわれ、その最期は修行を前にして「寵童・波々伯部某」と浴室に入ったところを暗殺されたという伝承が付されている(『野史』)。
細川高国と柳本弾正
政元には澄之以外にも養子がいた。細川高国(1484〜1531)である。
彼もまた養父に似て男色好きであったとされている。ただし、出典は後世の編纂物である。丹波出身で香西四郎左衛門(元盛)の弟、柳本弾正(賢治)との男色関係が伝えられている。
柳本弾正と言う者がいた。幼稚の時は美童だったので、高国が殊に男色にふけり、寵愛も勝れていた。成人になると身に余る俸禄を与えられ、栄耀は人々を越えた。
この『足利季世記』(別題『細川家略記』)は、織田信長の時代から江戸初期までに書かれた軍記とされるが、豊臣時代成立の可能性も指摘されている(和田英道氏「細川氏関係軍記考(二)」)。
いずれにしても後世のものであるから、書かれた内容すべてを事実として鵜呑みにはできないが、政元同様、武家の男色が将軍以外にも親しまれはじめたことが窺えるのは興味深い。同書で興味を引くのは、主君と家臣ばかりでなく、家臣同士、同胞間での関係が描かれていることである。
高国の侍に高畠甚九郎と云う美童がいた。柳本とは男色の因みがあり──。
高国を男色に耽らせた柳本弾正は、他の美童・高畠甚九郎とも関係があったというのだ。事実はともかく、この時代の武家衆道には貞操観念と呼べるものが薄かったようである。江戸時代の山本常朝は、一生に一人だけ愛することを男性同士の関係の理想としたが、室町時代にそのような精神性は見られない。
細川高国と柳本弾正はその典型で、そこに貴族的な享楽はあっても、『葉隠』で熱心に説かれる「忍ぶ恋」の面影を求めることはできないのである。
武家の間ではじまった男色の風俗が、成人武士と小姓児童と親愛の念を深めることはあっただろう。しかしそれはまだこの時、江戸時代の武家衆道や、僧侶と稚児の関係で見られたような永久不変の契りを強いるものではなく、文化的な遊戯のひとつでしかなかったのである。
讃岐守護・細川政之、若衆に心を迷わす
細川一族には、まだ他にも若衆好きがいることを書き加えておこう。讃岐・阿波守護であった細川政之(1455〜1488年)である。文明11年(1479)5月23日、壬生寺にて地蔵堂の堂舎修理を目的とする勧進の幸若舞が興行された。これに臨席した守護の細川政之が若衆に心を迷わせたと壬生氏の日記に書かれている(『晴富宿禰記』)。
讃岐守護・細河弥九郎(政之)はある若衆に心を迷わせ、見物の桟敷を(若衆の)楽屋に隣接する形で構えさせたと言う。堂東局の東西である。讃州・弥九郎は今日、見物に若衆を同輿せしめて浅橋に向かい、帰路も一緒であったそうだ。
一目惚れした若衆と一緒に幸若舞を楽しんだ後、同じ輿で帰ったのである。
政之は欲望に忠実な性分だった。放埒な性格は家臣の失望を招いたようで、『雅久宿禰記』同年8月11日条には「細川讃州弥九郎(政之)は、まったくしっかりしたところのない人であった。被官人たちは当主を別人に挿げ替えるための支度を整えたそうだ」とあり、家中で一騒動あったことが記されている。政治能力に問題のある人物は、好色面でだらしなさを発揮する傾向があったのだろうか。
細川一族には若衆好きが多い。細川幽斎の甥にあたる、雄長老(1544〜1602)は『古今若衆序』(1589)の著者であることが伝わるように、彼もまた若衆好きでこれをとても肯定的に書き記している。戦国時代の男色は、畿内の上級武士から広まったものであるから、細川一族の人々が男色に関心を示すのも不思議なことではない。反対に、身分の低い百姓たちはこれを蔑んで嫌っていたようである。
そうしてみると、一般に性的指向は、生まれついての先天的なものによって決定されるという認識が強いようだが、この時代の男色の「攻め」は、後天的な影響で拡散されていたように思われる。
地方の武家に広まった男色
そしてこの頃から、地方の武家社会にも武家男色の習俗が見られてくるようになる。文明12年(1480)、九州地方、筑前国に連歌師の宗祇が訪れると、この国を統治する陶弘詮が供応した。弘詮は周防国・大内家の家臣で、筑前の守護代であった。当時の大内家は西国一の大名として中央に強い影響力を有しており、当主をはじめ家中の侍は京文化に深い造詣があった。弘詮もまた武人であるとともに文人であった。弘詮の文芸コレクションはのちに毛利家の手へと渡り、現在に伝えられている。弘詮にとって一流の文化人である宗祇を守護代の館に招くことはまたとないイベントであった。
この時の様子を宗祇はこう記している。
此のあるじ、年廿の程にて、其様、艶に侍れば、おもふおり、ことなきにしも侍らでおぼえず、勤盃時移りぬ。
弘詮は色気のある20歳ぐらいの若者を侍らせ、宗祇と杯を交わしたようだ。京文化に親しみのある大内家では、既に男色の習俗を嗜む風が身についていたようである。
くだって大永5年(1525)の秋頃、宗祇の弟子である宗長が東国を訪れた時の『宗長手記』に、下野国の那須助太郎なる侍が、「愛着せし若きもの〈美童〉を討死させて、愁傷」したという記録が見える。
那須氏は関東八屋形のひとつに数えられるほどの旧族であった。同書には、駿河の今川家の家臣である三浦弥太郎が「愛着のわかき斎藤四郎」の病死を嘆く記事も見える。今川家も大内家と同じく京文化に親しむ大名として知られる。どうやら武家の男色風俗は、特に文化的志向の強い地方で受け入れられていったようである。
中央で流行を見せる男色はハイソかつデカダンな文化的遊びとして印象され、中央への憧れとともに地方武士の興味を誘い、全国へと拡散していったのであろう。世の乱れとともに頽廃的な気分に浸ることを是としてしまったのである。
こうして五山禅林の僧侶から吸収された男色趣味は地方にまで伝搬するようになっていったのである。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
ないしまさひこ。歴史家。昭和49年(1974)生まれ。高松市出身、相模原市在住。平将門、上杉謙信など人物の言動および思想のほか、武士の軍事史と少年愛を研究。主な論文に「戦国期における旗本陣立書の成立─[武田信玄旗本陣立書]の構成から─」(『武田氏研究』第53号)。著書に『平将門と天慶の乱』『戦国の陣 ...









コメント欄