「六本木・麻布・芝浦」都会の雑踏に埋没する、つわものどもが夢の跡
- 2023/02/21

「居酒屋」から「大人の社交場」に変貌
1978年に映画『サタデー・ナイト・フィーバー』が大ヒット。それで火がついたディスコ・ブームが全国に波及し、80年代になると若者の夜遊びには欠かせぬ存在になっていた。大きな雑居ビルに数軒のディスコが入り、繁華街では居酒屋と同じくらいディスコのネオンや看板をよく目にしたものだ。SNS や出会い系アプリもなかった頃、ディスコのチークタイムは、見知らぬ異性と知り合いになれる数少ない場所でもある。

1979年にオープンした六本木スクエアビルは、すべてのテナントがディスコで占められるディスコブームの象徴的存在だった。
大人の街といった印象が強かった六本木なだけに、新宿や渋谷のディスコよりは少し敷居の高さは感じるが。まぁ、ディスコはディスコである。当時の感覚では……そうだ。
この頃のディスコは、居酒屋に行くのと同じの気安い場所だった。入場料1500〜2000円でフリードリンク。親のスネを齧っていた学生のフトコロにも優しい。
六本木交差点のアマンドが、まだ白とピンクの派手なツートン屋根だった当時、店先の歩道はディスコに行く若者たちの待ち合わせで混雑していた。サーファー・ファッションが流行っていた頃。だが、大半はサーフィンなどやったことない“陸サーファー”である。T シャツやビーサンが目立つ、襟のついたポロシャツ姿は小奇麗な部類だろうか?


しかし、80年代中盤あたりから、その様相に変化が起こる。1984年にオープンした『麻布十番マハラジャ』は、それまでのディスコと比べて大きく豪華な設備で話題を呼んだ。シンセサイザーを多用するユーロビートがディスコミュージックの定番となったのも、マハラジャから始まったもの。ちなみに、バブリー・ダンスで再ブレイクした荻野目洋子の『ダンシング・ヒーロー』は、90年代の globeや TRF などに継承されてゆく“和製ユーロビート”の走りでもある。
この他にも「服装チェック」や「お立ち台」など、現代に語り継がれるディスコ文化(!?)の礎を築いた伝説の名店だった。
“格差”は興奮を盛りあげる舞台装置
いまは建て替えられて、あの当時よりはずっと地味な外観になったアマンド六本木店から、外苑東通りを東京タワーに向かって歩く。まもなく右手にディスコ全盛期の数少ない遺構であるロアビルが見えてくる。

この白く巨大な建物にも当時は2〜3軒のディスコがあり、週末にはエントランスの階段付近は大勢の客でにぎわった。10年ほど前に六本木クラブ襲撃事件の現場として世をにぎわせた場所でもある。色々な意味で六本木の名所的存在だったが、老朽化のため近く取り壊される予定。

テナントは去ってゆき、白かった壁には汚れが目立ち、なんだかとっても物悲しい。
ロアビルから右に曲がって鳥居坂を下る。坂を下り切って環三通りに合流し、そこから左に少し歩いたところにマハラジャはあった。閉店後は会員制クラブとなり、現在はカフェレストランとテナントは変遷しているが、エントランスのあたりには当時の名残も感じられる。




麻布十番駅からすぐの場所。だが、マハラジャがあった当時に大江戸線は開通していない。最寄り駅の六本木から徒歩15分はかかる陸の孤島だった。
しかし、それが好都合な者たちもいる。マハラジャは男性客だけでは入れないシステム。連れの女性がいない男たちは、道中で女性グループに声をかけて同伴をお願いするのだが。駅から店までのアプローチが短いと声かける暇がない。その目的を果たすのには、これくらいの距離がちょうど良い。閑静な高級住宅地の坂道は、繁華街のナンパ・ストリートみたいになっていた。
同伴してくれる女性が見つかっても、そこからまたさらに苦労を強いられる。週末ともなれば500メートル以上にもなる入店待ちの長い行列がつづく。2時間以上も待たされてやっとエントランスに辿り着くと、そこで黒服やポーターから服装を入念にチェックされる。ドレスコードにあわせてジャケットを着用していても「イケてない」と判断されたら門前払い……。
現代では考えられない殿様商売だった。が、客もそれを望んでいた。服装チェックをパスすれば「自分はイケてる」と自尊心を満足させられる。そのために高価な DC ブランドをローンで買って、その返済にアルバイトに明け暮れる学生も多かった。
しかし、ヒエラルキーにはまだ上がある。陸の孤島ではクルマの真価が発揮される。高級外車で乗りつける上客には、店先の幹線道路が駐車スペースに提供されて行列をスルーして VIP ルームに案内されてゆく。
あきらかな格差を見せつけられるのだが、それに不満や反発を覚える者はいない。テンションを下げるどころか、むしろ、それには一般客の気分を高揚させる効果もあった。
現代のように階層が固定された社会ではない。「いつかは自分も」と、将来に夢や希望がもてる時代だった。だから、格差を妬むよりもそれに憧れる思いのほうが強い。実際、当時は新卒サラリーマンに100万円を越えるボーナスが支給されることも珍しくはなく、賃金は上昇をつづけていた。就職さえすれば高級外車の頭金くらいすぐに貯まる。
そういえば、マハラジャのコンセプトは「人々に夢と感動を与える」だったとか。店先に高級外車を停める VIP の姿に、近い将来にそうなるはずの自分を重ねあわせる。たしかに、夢と感動は得られそうだ。前を向いて生きることができた古き良き時代だったと思う。
ディスコ・ブームを終わらせた大事故
麻布十番から六本木に戻る。アマンド前の交差点を渡り外苑通りを乃木坂方面へと歩く。間もなく右手に見えてくるのは防衛庁……ではなかった。防衛庁は2000年に市ヶ谷へ移転して、いまは東京ミッドタウンになっている。そういえば、六本木駅の案内板にも「東京ミッドタウン」「六本木ヒルズ」などが大きく掲示されている。けど、80〜90 年代には存在しなかったランドマークばかり。現代人がタイムスリップすると、とたんに迷子になりそうだ。東京の街の変化は激しいが、とりわけ近年の六本木の変貌ぶりは凄まじい。
東京ミッドタウンとは外苑通りを挟んで反対側の路地を入ると、小さな地蔵がぽつんとある。当時を知る人なら、そこに地蔵が設置された意味がなんとなく推測できると思う。そこは「トゥーリア」があった場所だ。


バブル景気が本格化した1987年に開店したトゥーリアは、マハラジャで成功をみたディスコの高級路線をさらに進化させた店。1棟の大きな建物にディスコやレストラン、バーが併設され、宇宙船をコンセプトに贅を尽くした照明装置を完備していた。高級ディスコのマハラジャを越えた“超高級ディスコ”としてテレビや雑誌にもよく紹介され、各界の有名人も大勢やって来た。
そんな注目の場所で惨劇が起こる。1988年1月5日、この店のウリだった天井の可動式巨大照明装置が落下した。フロアにいた客たちが下敷きになり、3名の死者と多数の負傷者が発生している。人々にあたえたインパクトは凄まじく、マスコミの報道合戦は開店時よりもさらに加熱した。
後の時代には「あの事故がディスコブームを終わらせた」と“トゥーリア戦犯説”が唱えられるようにもなったのものだが、しかし、事故後もしばらくディスコ・ブームはつづいていた。
恐竜と同じ絶滅への道を辿る
恐竜が巨大化をつづけてやがて絶滅したように、ディスコもまた同じ道を歩みつづける。六本木のような繁華街の密集地ではもはや収まり切らず、ウォーターフロントと呼ばれる湾岸エリアに新天地を求めて巨大なディスコが出現した。芝浦に「ジュリアナ東京」が開店したのは、バブル景気が弾けた1991年のこと。空き倉庫を有効活用するために考えられた苦肉の策だったという。


当時の田町駅東口には、ゾロゾロと群れをなして歩くワンレン・ボディコンの派手な女子たちの姿が見られた。週末のジュリアナ東京には2000〜3000人の客が押し寄せる。人が密集した館内は空調が追いつかず、かなり暑かった。ジュリアナ東京で名物となっていた大きな扇子も、暑さしのぎに風を送るために用いたのが最初だったという。
また、扇子とともに有名だったのがお立ち台。最初に登場したのはマハラジャだったといわれる。ダンスフロアの混雑を回避するため、客たちがフロアの隅に設置されたスピーカーボックスに上がって踊るようになり始まったものだったとか。
ジュリアナ東京ではそれを「設備」として導入した。1 人か2人がやっと乗れる程度の小さなスピーカーボックスと比べて、ジュリアナのお立ち台は数十人が横一列に並んで踊れる。その壮観な眺めが話題を呼んで客は増えつづけた。
しかし、誰もがお立ち台に上がれるものではない。そこは「いい女」「イケてる女」に与えられる特別のステージ。リピーターになって黒服やポーターから顔を知られる域にまでいかないと、なかなか上がれるものではなかっただろう。
ここにもまた格差が存在する。とはいえ、お立ち台で踊る大半は、ふだんは自分と同じ学生やOL。埋まらない格差ではない。いつかは追いつける。そう思えば萎えることはない。いつの日か、お立ち台の晴れ舞台に立つ自分の姿を投影して興奮を覚える。

終わりの見えない低成長の時代、格差は埋めようがないほどに広がった。誰もが諦めて萎えてしまう。ディスコ・ブームもそこで終焉……かつてジュリアナがあった建物の前は人通りもなく、閑散とした場所に戻っている。
夢の跡。かつての熱狂を想像することは難しい。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。





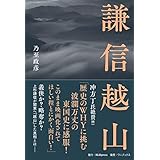




コメント欄