※ この記事はユーザー投稿です
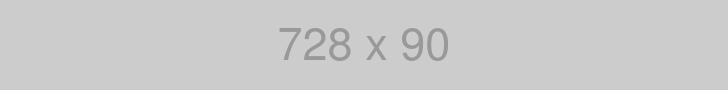
案外知られていない江戸時代の貨幣制度 ~右往左往した変遷の歴史~
- 2022/04/25

一方、時代劇の定番で悪代官と越後屋が「これはほんの手土産で」「越後屋、そちも悪よのう」というシーンがあります。このシーンで越後屋が持ってきた菓子箱の底には小判がぎっしりと詰まっていました。ですので小判、寛永通宝というのは良く知られています。
しかし、寛永通宝を何枚集めれば小判1枚分になるのか、ということはあまり知られていません。というのも江戸時代の貨幣制度は現代とは全く違っており、説明なしではとても理解できない代物だったのです。
時代劇でそういう説明が行われることもないので、なんとなく「小判1枚は1両」「寛永通宝1枚は1文」ということ位しか知られていない訳です。
今回は江戸時代の貨幣制度を詳しく説明し、ご理解頂いた所で江戸時代の貨幣の変遷の歴史を述べてみたいと思います。
元は武田信玄が考えた制度
江戸時代の貨幣制度を整備したのは徳川家康ですが、家康は武田信玄が自分の領地内に敷いていた貨幣制度をモデルにしました。武田信玄の領地内には金鉱が多数あったので、それで独自の金貨を作り、貨幣制度を定めていました。これを甲州金と言い、一番、高額な金貨が1枚で1両、その下に「分」という単位をもうけて4分で1両、「分」の下に「朱」という単位をもうけて4朱で1分、という4進法による区分をしました。そして一番下の単位である「1朱」の下に「文」という単位を設けて銅銭を充て「250文で1朱」と定めていたのです。
信玄の時代には中国、朝鮮半島からやって来た永楽通宝に代表される「渡来銭」と呼ばれる各種の銅銭があり、それをそのまま「1文の貨幣」としました。つまり、小判1枚は一両であり、それは文に換算すると4000文になるので、寛永通宝を4000枚集めれば小判1枚分に相当したのです。
ちなみに甲州金は残されている数が少なく古銭コレクターには垂涎のアイテムとなっています。下記の写真は甲州金の一分金です。

金座の制定
家康は後藤光次に命じて金貨を鋳造する金座を作らせます。従って江戸時代の金貨は必ずどこかに「光次」という文言が入っています。金座で最初に作られたのは一両小判と一分金の2種類で通称、慶長小判、慶長一分金と呼ばれています。これらの金貨は85%以上の純金で出来ており、数も少ないので現在でも非常に高価な値段が付きます。


小判は常に「一両」で価値は変わりません。ですが幕府の財政は年月が経つに従って傾いていき、五代将軍綱吉の時には小判の金の含有量は初期の慶長小判の半分になってしまいました。しかし八代将軍吉宗の時に持ち直し慶長小判と同等の含有量に戻ります。
しかし幕末に向かうに従って再び財政は傾いていきました。経済状況が悪化するたびに一両小判の金含有量は減らされ、江戸時代を通じて10回の小判の金含有量の改定が行なわれました。
小判は裏面に元号を略した刻印を入れたので、この刻印により「いつ、作られた小判なのか」が判定できます。例えば下の写真の場合は ”保” の刻印があるので「天保年間に作られた小判」だと分かるのです。

江戸時代も後半に入ると、ついに小判相場というものが現われ、銀や文との交換率が裏面の刻印によって変わるという状況が発生してしまいます。
家康の目指した定位貨幣制度は残念ながら江戸後半期には形骸化してしまったのです。もっとも江戸の一般庶民には小判は「縁遠いもの」だったので、ほとんど影響はなかったようです。
銀座の制定
貨幣の単位は、両、分、朱、文であり、金座で両と分が作られていたので、当然、銀座では「朱」が作られていたと思われるでしょう。しかし、そうではありませんでした。なぜなら銀には江戸時代以前から相場という物があり価値が流動的だったので「定位貨幣」が作れなかったのです。そこで銀座では「秤量貨幣」という特殊な貨幣(と言えるかどうか疑問ですが)が作られていました。それが以下写真に示す二種類の物です。


一番、左側の物は「丁銀」、右隣の物は「豆板銀」と呼ばれるもので「重さを測って、その時の銀相場に従って価値が決まる」というもので、初期にはこれらが「朱」の代替役を務めていました。
もし、少し重すぎたら切っても構わない、という物で、実際に切られた状態の物も残っています。何しろ「重さを測って、その時の銀相場に従って価値が決まる」ので重さも、まちまちでしたが丁銀は商業取引用で豆板銀は一般庶民用として使われていました。しかし「重さを測って銀相場を調べないと価値が決まらない」のでは一体、いくらの価値があるのか分からず、使う方にも使われる方にも不便極まりないものでした。「朱の単位の貨幣が無い」のはあまりにも不都合だったのです。
そこで明和9年より銀座で二朱銀と一朱銀の鋳造が始まります。それが右の2枚で通称「南鐐二朱銀、一朱銀」と呼ばれます。


しかし銀の相場は流動的だったので裏面に「銀座常是」と明記し「相場に関係なく、これは二朱、一朱の価値がある」こととし、念のために表に「何枚持ってくれば一両小判に替えてやるから」という保証書きまで入れることになりました。江戸時代の戯作本や読本によく「南鐐、なんりょう」と言う言葉が出てきますが、それは、この二朱銀のことを指しているのです。
これで一応、定位貨幣のラインナップが揃った訳です。こうして定位貨幣が出たにもかかわらず、相変わらず丁銀、豆板銀も作られ続けます。それは「長年の習慣」で商取引などで丁銀、豆板銀が使われることが定着していたことが理由で一般庶民にはあまり関係のないことでした。とにかく「なんりょう」ができたおかげで庶民の暮らしは非常に便利になったのです。
寛永通宝の発行
当初は渡来銭に頼っていた銅銭も寛永13年に「寛永通宝」という幕府発行の正式銅貨を作ることにしましたが、何しろ大量に作らなくてはならないので許可制にして各所に「銭座」と呼ばれる鋳造所を作りました。銭座は当初は14カ所でしたが、いくら作っても足りないので、どんどん増えていき最終的には42箇所にもなりました。そして寛永通宝は各銭座で違いがあり区別する事が可能で、しかも時代による変化もあるためコレクターにとっては「いくら集めても集めきれない」という位にバラエティに飛んだ貨幣となっています。
銭座で作られた寛永通宝には1文銭と4文銭があり、裏が「波模様」になっているのが4文で、そうでないのは全て1文です。1文銭の裏面は文という字が入っていたり、何も書いてなかったりで色々でした。

「朱」の貨幣が無いことによる弊害
上記でも触れましたが、当初は「朱」に当たる貨幣が無く、「文」の次は、いきなり「一分」でした。そして一分は1000文に相当します。現代風に言うと10円玉の次が一万円札で、その間の貨幣、紙幣が全く無い、というのと同じです。一般的に寛永通宝は100枚をワラの紐に通して持ち歩くのが常でしたが1000文となると、この100枚の束が10本となります。
下記に写真をお見せしますが、こんな量になってしまうのです。重さは3.75kgもあり、持ち運びも大変でした。ちなみに1000枚を称して「一貫文」と言います。

仮に旅行にでも行こう、となった場合、一分金を持って行って両替屋で文に変えると、これだけの量の銅銭を受け取ることになってしまうのです。これでは重すぎて旅行にも支障をきたしてしまいます。
当時の旅館である旅篭屋の一泊料金は300文から400文でしたが、それを払うのに、えらい苦労をしていたのです。「なんりょう」が出てきてくれて、やっと「ちょうど良い量の文」に交換できるようになり、支払いも楽になったのです。
そういった事情もあり、二朱銀、一朱銀は一般庶民から親しまれ、重宝がられた貨幣でした。
一文を現在の円に換算するといくらくらいなのか?
江戸時代に書かれた色々な本を読んでいると、当然ながらお金に関する話もよく出てきます。しかし江戸時代と現代では状況が違い過ぎて比較しても「意味が無い」物が多いというのが実感です。例えば滝亭鯉丈の「浮世床」という本を読んでいると、こんな会話が出てきます。
主人:「繰り出す前に何か食べるか」
お客:「うなぎを買いにやりは?」
主人:「どうか、ということか。ちょっ、いじめるの」
といって南鐐二朱銀を放って渡す場面が出てきます。つまり「うなぎの蒲焼二人前で二朱」ということです。
えらく高そうですが、それはそうでしょう。当時は養殖うなぎは存在せず輸入物もありません。全て「漁師が取ってきた天然うなぎ」なのです。数は非常に限られており高額でした。
昭和初期の話ですが、客として訪れた家で、うな丼を出された場合は半分だけ食べて半分は残すのが礼儀だったそうです。つまり半分は、その家の子供の為に残してあげるのです。それほどに、うなぎというのは高価で滅多に食べられる物ではなかったのです。
また山東京伝の話として「かかぁの銭入れから三文くすねて屋台のさざえの串焼きを買い食いしたら、あまりの美味さに忘れ難し」というのがありますが、現代では屋台で「さざえの串焼き」は売っていませんので見当がつきません。三文なのだから、相当に安いことは安いのでしょうけれど。
しかし何とか「現代と比較可能な物」を見つけました。それは「ベテランの大工の日当」です。最後の戯作者と呼ばれる仮名垣魯文の書いた「安愚楽鍋」という本の中で大工のベテラン職人が以下のようなことを言っているのです。
「こちとら、かかぁと三人のがきを抱え、一日に二朱の札がなけりゃ身動きひとつできねぇ体だが、天下晴れてのお職人さまだぁ」
つまりベテランの大工職人の日当は二朱だった、ということになります。
大工さんの仕事というのは今も昔もそう、大きくは変わりません。建築工法こそ進歩しましたが今でも「昔ながらの工法にこだわる職人肌の大工さん」はいます。そういった方の日当はいくらなのか調べて見ました。
厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査によると「経験年数が15年以上の大工さんだと平均年収は約425万円」だそうです。週休二日で一か月に20日働くとして年間で240日です。つまり、425万円÷240=17708円が日当となります。
まぁ18000円というところでしょうか。結構、高額ですよね。二朱は500文ですので、18000円÷500=36円ということになります。つまり1文=36円となるのですが、山東京伝の話とも何となく、この数字なら納得できます。
串焼き一本、100円なら妥当ではないでしょうか。また井原西鶴の日本永大蔵の中で農家の人が初物のナスを「1つなら2文、2つなら3文」と言って売る場面が出てきます。初物は珍重されたので1文=36円なら、何となく納得できる値段ではないでしょうか?
とはいえ、やはり江戸時代と現代の物価を比較するのは少し無理がありそうな気はします。しかし、大体の見当は付けられたのではないでしょうか?
天保通宝について
古銭コレクターにはおなじみの「天保通宝」と言う貨幣があります。小判型をした銅銭で裏には「當百」とあることから100文にあたるらしいことが分かります。
「もし1文が36円なら天保通宝は3600円ということになる。高すぎないか?」と言う疑問が湧くと思います。当然の話で高すぎます。実は天保通宝は江戸末期に出された貨幣で発行当時から「せいぜい80文」で、やっと通用した貨幣で経済的に追い込まれていた江戸幕府が苦しまぎれに出した物です。
Wikipediaでも「質量的に額面(寛永通宝100枚分)の価値は全くない貨幣」であり、発行当時、世の中を混乱させた貨幣として有名です。それでも江戸幕府は天保通宝を大量に発行し続けたため、天保通宝が世の中に溢れてしまい明治政府は新円との交換レートを一両=6500文という本来の4000文を大幅に上回るレートにせざるを得なくなったくらいなのです。つまり、天保通宝は「100文の価値は最初から無い貨幣」なのです。
寛永通宝は江戸時代を代表する銅銭ですが、天保通宝は幕末の苦し紛れの産物である、ということは覚えておいて損はありません。実際、時代劇でも天保通宝は、まず登場しません、なぜなら、「幕末にならないと出てこない貨幣」だからです。
あまりにも数が多い為、現在の古銭相場でも一枚200~300円くらいで買えます。見た目がちょっと立派で大きいので魅かれるものがありますが、実は滅茶苦茶に嫌われ、古銭市場でも溢れかえっている貨幣なのです。
江戸時代も安政、天保、といった最後期の時代になると、小判の金の含有量は大幅に下がり、以前は金で作られていた一分金が銀で作られるようになります。

都内のある工事現場で工事中に江戸時代の壺が出てきて、その中に大量の一分銀が入っているのが見つかりました。新聞も「お宝発見!」と書き立てました。一応、元所有者と思われる商家の調査なども行われましたが遂に判明せず、出てきた大量の一分銀は発見者4人の物となりました。
もし、これが江戸時代初期の物であれば一分銀ではなく、一分金が入っていたでしょう。そうしたら本当にお宝になるところでした。ですが残念ながら発見された物は江戸末期の一分銀で、古銭商が付けた買い取り額は全部で30000円。一分金は良い値が付きますが、一分銀は値が付かないのです。発見者4人で分けたら一人あたり7500円にしかならなかったそうです。
江戸幕府末期の財政苦境は、こんなところにまで影響していたという変な一例となってしまいました。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。






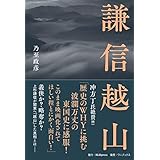





コメント欄